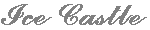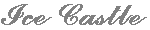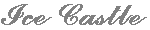 | ―氷の城―15 |
城主が姿を消した後、アストリッドは珍しく怒りに任せて、香料の入った銀の小箱をテーブルから取ると壁に投げつけた。 小箱の蓋が飛んで、中から貴重な粉がこぼれ、床に散った。
それは城主から人づてに贈られたものだった。 その他、髪飾り、スカーフ、手袋などいくつも貰ったが、一つも直に渡されたものはなかった。
「なんでこんな扱いなの」
歯を食いしばって、アストリッドは呻いた。
「ひどいわ。 この間新しい道化師が来たと聞いたけど、まだ顔を見たこともないのよ。 花摘みも駄目、礼拝堂にさえ行けない。 まるで囚人だわ!」
その夜、ケイティが寝支度を手伝って部屋を出た後、アストリッドは考えこみながらベッドを見つめた。 このシーツ、そして上掛け。 細く切ったらどれほどの長さになるだろう。
以前に聞いたことがあった。 どこかのお姫様はシーツを裂いて縄を編み、高い塔から脱出して愛しい人の元へ走ったそうだ。
愛しい人――瞼の裏に、塔の下を毎日通る若者の姿が一瞬浮かんで消えた。 アストリッドは固く目を閉じて、自分の心に訊いてみた。
――あの人が好き?――
はっきりとは言い切れなかった。 城主の男らしさも嫌いではない。 むしろ好ましいのだ。 もっと大事に扱ってくれさえすれば……
「どっちみち、あの若者だってユージン様の配下なのだから、私を連れて逃げることなんかできない」
出るのは吐息ばかりだった。
翌晩から、ぴたりと城主の訪れが止んだ。 同時に城全体の空気が沈み、前は風に乗って聞こえていた大広間の喧騒がまったく響いてこなくなった。
恋人としての勘で、アストリッドは悟った。 城主の具合が悪くなったのだ。
そうなると、言い争いなど問題ではなくなった。 会いたい。 もし重態ならわずかの間でもいいからそばにいたかった。
だが、訴える相手は現れない。 ジャレッドでさえアストリッドの存在を忘れてしまったようで、彼女は塔の部屋で一人やきもきすることしかできなかった。
三日後の早朝、鐘楼の鐘が鳴った。 それは弔鐘。 身分の高い人がみまかったときに鳴らされる鐘だった。
背景:b-cures
Copyright © jiris.All Rights Reserved