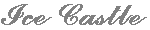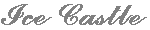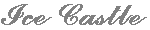 | ―氷の城―14 |
人の役に立ったこと、しかも相手に認められたという事実が、アストリッドの心に華やぎを運んだ 翌日からもう隠れずに、彼女は顔が見える程度に窓を開いて、若者が通るのを待つようになった。
彼もまた、単に歩き去るのではなく、塔に近づくと頭をもたげて窓を探した。 そして、アストリッドの愛らしい顔を見つけると瞳が輝き、口元がわずかにほころんで微笑らしき影を作るのだった。
たったそれだけのことだった。 なぜか彼がおなじ道を辿って帰ることはないので、一日にわずか一回、ほんの数分の出会い。
それでも、二人の間には確実に何かが通い始めていた。
あの若い騎士はどんな仕事をしているんだろう、と、アストリッドは考えた。 城主の警護、町の治安維持、それともお傍仕えだろうか。 もし彼がジャレッドの代わりに散歩の供をしてくれたら、とふと思い、小間使いの他は誰もいない部屋で赤くなった頬に両手を当てたりした。 耳の奥で強く脈の音が聞こえる。 じっとして見えても幹の中でたくましく樹液を吸いあげて伸びていく森の木のように、アストリッドの心は外見からわからない変化を遂げつつあった。
その夜、一週間ぶりに城主が忍んできた。 いつもに増して彼の体は熱っぽく、どことなく焦れた気配があり、アストリッドまで落ち着かなくなった。
筋ばった男の腕を枕に横たわりながら、アストリッドは思い切って尋ねてみた。
「体のお具合は? 私にもお世話をさせてください。 こんな塔に離れているのは寂しいです」
本心は寂しいよりも不安だった。 城主のそばにいれば余計なことを考えずにすむ。
だが、アストリッドの申し出を聞いたとたん、城主は上掛けをはね上げてガウンで体を包み、乱れた足取りで暖炉に近づくと寄りかかった。 かすれの入った声が響いた。
「よせ。 そなたはここにいればよいのだ。 何も考えず呑気にしておれば」
「なぜです!」
アストリッドの声も濁った。
「私は殿様のもの。 そうではありませんか? どうして殿様の暮らしをわずかでも分け合ってはいけないんです? 口出ししようとか見せびらかそうなどと思ってはいません。 人目につかないようにおとなしくしていますから、ただお傍に……」
「だめだ!」
激しい怒りと拒絶だった。 立ちすくむアストリッドを残して、城主は荒い足取りで隠し戸から立ち去った。
背景:b-cures
Copyright © jiris.All Rights Reserved