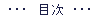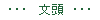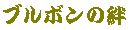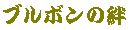

−78−
さすがに心が波立った。 マールは勉強するのに気が散ると言って、シルヴィーを部屋から出し、窓辺にもたれて考えに沈んだ。
――幼なじみの婚約者なら、初恋ってことね。 それなら、たまに会ったときに抱き合わないのは、なぜ?――
友達でも手ぐらい握るだろう。 しかし、二度目撃したシルヴィーとセルジュは、ただ話をしていただけだった。 男同士のようにさっぱりと。
――そうだ。 セルジュはあの兄妹の面倒を見ると言ったわ。 妹だけじゃなく。 あれは親代わりになるという意味のはず――
ほっとして、マールは肩の力を抜いた。 シルヴィーの言葉は、思い込みなのだ。 小さい子が、『私、大きくなったらお兄ちゃんのお嫁さんになるの』と言っているのと同じで、夢の一種なのだ。
日がとっぷりと暮れてから、コンデ公夫妻は屋敷に戻ってきた。 二人とも疲れていたが、機嫌はよさそうだった。
出迎えたマールに、エレは銀色の小箱を渡しながらウィンクした。
「ルイ王はずいぶん落ち着いて、冷静になっていたわ。 今度のことではひとかたならず世話になったから、御礼したいって。 これがあなたの分」
「私に?」
「そう、強い女性はコンデ家の伝統だな、という言葉を添えてね」
中を開けてみると、ルビーを散りばめた豪華なブローチが入っていた。 通りすがりに箱を覗いて、フランソワが言った。
「高そうだが、そんなものより切れのいい剣のほうが欲しかっただろう」
マールは答えずに、ただ微笑んだ。 今ではブローチも嬉しい。 母に見立ててもらった臙脂〔えんじ〕色のマントをこのブローチで止めて、セルジュの元へ馬を飛ばして行きたかった。
夕食の席でようやく、マールは両親とゆっくり話し合うことができた。
フランソワは、燕亭をクロードに譲るのをいいアイデアだと思っていた。
「酒場の主人なら足が不自由でも充分できる。 もともと犯人の財産だから、ただでやっても国王の懐は痛まないしな」
「ただでいいって?」
マールは喜んで身を乗り出した。
焼き肉を切りながら、フランソワは妙な目つきで娘を見た。
「なんでそんなに嬉しいんだ? まるで身内のことを心配しているみたいだな」
「いや、だって、殺されそうになって気の毒だったし、私が現場を見つけたから」
なんだかマールはしどろもどろになった。
背景:CoolMoon
Copyright © jiris.All Rights Reserved