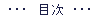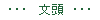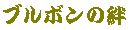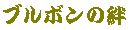

−37−
優雅に受け答えしながらも、マールは気が気ではなかった。 早く帰らないと、忙しい父はまた騎兵隊の閲兵やら演習やらで家を出てしまうかもしれない。 焦りぎみのマールは、ぎこちなく立ち上がってまたよろめいて見せた。
「水で冷やしたぐらいでは、腫れは収まらないようですわ。 心細いので、やはり家へ帰ります」
「お気の毒に」
アドリアンは優しく言うと、すぐ馬車を呼びに行ってくれた。
「うちまで送ると言い出されないで助かった」
コンデ家お召し抱えの御者が鞭を鳴らして門を通り抜けるとすぐ、マールは胸をくつろげて足を伸ばした。 ついでに帽子も脱いでポンと向かい側の座席に放った。
できるだけ急がせたので、馬車は風のように走った。 そのおかげで、マールはせっかちな父がデュパンを従えて馬に乗ろうとしているところに、危うく間に合った。
髪を乱して酒場女のような格好で馬車から転がり出てきた娘を見て、フランソワは誤解してしまった。 口髭がぴりぴりと震え、大音声が馬屋に響き渡った。
「襲われたのか? 誰だ! わたしが一突きで成敗してやる!」
「違います!」
大急ぎで父に飛びついて、マールは馬屋の奥、誰の耳も届かないところに引っ張っていった。 そして、なおも用心して耳元に口を寄せ、ごく小さな声で囁いた。
「クルスナールという男を見つけたわ」
とたんに、フランソワの顔が変わった。 まったくの無表情になり、目だけが怖いほど鋭く光った。
「なんだと?」
「新しく王様の側近になった若い貴族。 ジョゼ・クルスナールと名乗っていて、北部から来たはずなのに、お母様と同じ訛りがあるの」
フランソワの口が一文字になった。
「最悪だな」
マールもそう思った。
ルイ国王は絶対権力者として、すべての情報を確保しようとし、すべての実務をこなそうと日夜努力していた。
つまり、彼は誰も信用できなかったのだ。 特に警戒していたのが、他ならぬ親族の者たちで、王の座を狙っているのではないかとスパイを潜入させて常に見張っていた。
その親戚たちの中で、国王がもっとも煙たがっているのが、フランソワ・コンデ公爵なのだ。 その彼が、国王の身が危ないと忠告しても、逆に疑われるのがおちだった。
悩んだときの癖で口髭を痛いほどひねりながら、フランソワはマールに言い含めた。
「まだ誰にも言うなよ。 アンリたちにもだ。 そやつが本当にあの一味なのか、それとも名前だけが同じで、ただの偶然の一致なのか、まず調べなければ」
背景:CoolMoon
Copyright © jiris.All Rights Reserved