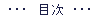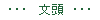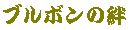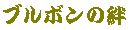

−36−
マールの頭は忙しく動いていた。 これが例のクルスナールだとしたら、潜入先はヴェルサイユ宮殿の最奥の間、つまりルイ王のすぐそばということになる。 なんという大胆不敵さだろう。 『テュイルリーの薔薇』を合言葉にした陰謀団は、国王の暗殺を狙っているのか?
一刻も早く父に知らせなければ。 マールはとっさに、通路の横に飾ってある牧神の彫像の台座に靴を打ちつけて、うまく踵を折ってよろめいた。
「いたっ」
驚いて、同行者たちが振り返った。 エレが心配そうに尋ねた。
「どうしたの?」
マールは顔をしかめ、足を軽く引きずってみせた。
「引っかけてしまって。 足首をくじいたみたい」
「あらあら。 冷やさなければ。 歩ける?」
「ええ、なんとか」
青年たちの間から、鹿のような茶色の目が印象的な背の高い男が進み出て、丁重に申し出た。
「わたしが噴水までお運びしましょう」
そして、まだマールがいいとも悪いとも言わない内に、いきなり軽々と抱き上げて歩き出した。
うわっ!――いらぬお節介に、マールは目を白黒させた。 エレは面白がってにやにや笑っていた。
「よろしくお願いね。 治らないようだったら馬車に乗せてやって」
「かしこまりました」
青年貴族たちに囲まれて賑やかに去っていく母の後ろ姿を、マールは男の肩越しに恨めしそうに見送った。
鹿の目をした青年は、なめらかに歩きながら自己紹介した。
「アドリアン・フェデと申します。 国王の衣装係で」
「初めまして」
マールはやせてはいるが筋肉質だ。 見かけより重いだろうと気遣いながら、落ち着きなく答えた。
噴水の縁にふわりとマールを下ろして座らせ、アドリアン青年は微笑んだ。
「一幅の絵のようです。 お母様とは違う意味で、お嬢様もお美しい。 狩りの女神ディアーヌのようです」
狩りの女神? うまい形容じゃないか、とマールは密かに思った。 長身でがさつな自分を称えるなら、それぐらいしかいないだろう。
これだけは兄たちにも褒められる長く反り返った睫毛の下から、せいぜい女らしく青年を流し目で見て、マールははにかんでみせた。
「ありがとう。 あなたもユピテルのように凛々しくていらっしゃるわ」
「それはどうも」
なぜかこんなありきたりのお世辞に、アドリアンの額がぱっと赤らんだ。
背景:CoolMoon
Copyright © jiris.All Rights Reserved