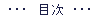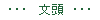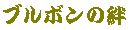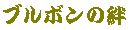

−21−
『シモーヌ』になればいつでも会える、と、マールは思い込んでいた。 ところが翌日の午前中、まだ両親が家に戻ってこないのをいいことに急いで変装を済ませ、わくわくしながら裏口から出たにもかかわらず、その日は園丁もセルジュもまったく姿を現さなかった。
つまんない――半時間以上、頭巾の陰の耳をそば立たせながら道を掃き回って、裏口あたりはかつてないほどきれいになった。 だがカルナヴォン邸は静まり返っている。 そろそろあきらめて庭に戻ろうとしたとき、意地悪げな笑い声が聞こえて、生垣の端から下働きの娘が出てきた。
年ごろはマールと同じぐらいだろうか。 ひどく痩せてそばかすだらけだが、孔雀のように気取って歩いてくると、顎を突き出して横柄に言葉を投げつけた。
「あんた同じところを何遍掃いてるの? 昨日みたいにセルジュが出てこないかなって思ってるんでしょう。
残念でした。 セルジュはね、よそへ連れてかれたの。 後押しをしたいって貴族が現れて、昨日旦那様と話をまとめて、とっくに引越しちゃったのよ!」
マールの眼が皿のように広がった。
「どこへ?」
娘は憎たらしそうに口をひん曲げた。
「さあね。 自分で探したら?」
さっとスカートで地面をかすめて向きを変え、孔雀娘は気取って帰っていった。 マールはすごい渋面になって、その後ろ姿めがけて盛大に箒で埃を巻き上げてやった。
それからの時間は、ひどく退屈に感じられた。 せっかく色男の泥棒という面白いものを発見したのに、するっと手の中から逃げられた気分だった。
行儀悪くソファーに寝転んで両肘をつき、顎を載せて、マールは思いを巡らせた。
――早業のジャックか…… また会えるかな。 それとも、これっきりかしら――
なんだか胸の片隅に甘い痛みが走った。
その同じ日、昼食を終えたシャルルは、従者のベネデッティと、ビロードの上着に着替えたセルジュを連れて、ドゥ・マレ通りを歩いていた。 三人はこれから高名な宮廷画家フィリップ・ド・シャンパーニュのアトリエを訪れるところなのだった。
若い画家志望の青年たちは、腕のある大画家に弟子入りして技術を磨く。 才能を認められれば、まず背景、静物などの小物、そしてついには人物や構図まで任せられて師匠の代作をするようになり、やがて独立していく、というのが一般的な出世の道筋だった。
大きな木のアーチをくぐって、通りの外れにあるアトリエに入るとき、セルジュは落ち着いていた。 これまでほど自由はきかなくなるかもしれないが、パリに住みかがあれば仲間と連絡が取れるし、泥棒稼業もできる。 それに、これからは堂々と絵が描けると思うと、嬉しくもあった。 こういう大画家の仕事場なら、黒鉛の芯を木でくるみ革紐で結んだ『鉛筆』という新しい道具を持っているだろう。 それでデッサンをするとたやすく細い線が書けるそうなので、セルジュは密かに楽しみにしていた。
背景:CoolMoon
Copyright © jiris.All Rights Reserved