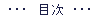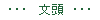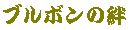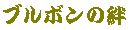

−102−
やがて着いたトーメ邸では宴会らしい宴会はなかったし、わずかな客たちもそんなものを期待してはいなかった。
なんとか午前中起きていたトーメは、到着時には半分うつらうつらした状態で、新しい義父母に挨拶し、妻に家令のオートゥイユと秘書のガニシェを紹介するとすぐ、寝室へ引っ込んでしまった。
トーメ自身は半分空をただよっているかもしれないが、ガニシェはなかなかしっかりした人物で、客たちを丁重に広間へ案内した。
久しぶりに会ったコンデ一家は、昼食までトランプをやり出した。 一番強いのがアンリで、次がエレ、最も弱いのが、切り札を出す決断力にとぼしいシャルルだった。
フランソワを交えて賑やかに騒いでいる家族を離れて、マールは衣装を着替えると庭に出た。 実家からついてきた小間使いのジャンヌマリーが後に従おうとしたが、マールは断った。
「長旅で疲れたでしょう? 部屋で休んでいて。 遠くへは行かないわ。 約束するから」
意外にも、トーメ邸は建てられて間もなかった。 後で聞いたのだが、領民の仕事を作るためにわざと大掛かりな土木工事をしたということだ。 つまり失業対策だったわけだ。
建物は最新式で美しいが、庭ははっきり言ってお粗末だった。 屋敷の周りは木も草もないただの空き地で、少し離れたところにはぼうぼうと生い茂っている。 屋敷の主はいつも上を見ているから、庭なんか目に入らないのだろうとマールは思った。
剥き出しの地面を歩いて、からみあうように枝の伸びた藪に足を踏み入れたとき、すっと手を引かれた。 そして次の瞬間、マールは愛しい人の腕の中にいた。
マールの眼に涙があふれた。 大きく盛り上がって頬に流れ、襟のレースに落ちかかった。
「ひどい! ほんのちょっとの間でも、私が裏切ったと思うなんて!」
「許してくれ、俺の大切な天使」
セルジュは苦しげに胸を上下させた。
「またシルヴィーの口車に乗ってしまった。 だが今度こそ、あいつも年貢の納め時だ。 浮気をばらしてやると言ったから、泡を食って逃げ出したそうだ。 たとえうまく逃げ延びたとしても、大親分が死ぬまでは二度と国内には戻ってこられないだろう」
「もうあなたと離れたくないわ」
胸をぐいぐいと押してくる栗色の頭に、セルジュは夢中で頬ずりした。
「戻ってくる。 修業が終わったら、ここへ飛んで戻ってくる!」
年明け早々に、マールは元気な男の子を産んだ。 喜んだトーメがまずステファーヌと名づけ、初めて祖父となったフランソワが自分の名をぜひ継がせたいと言い張り、伯父のアンリやシャルルまてが口を出して、ついに赤子の洗礼名は七つにまで膨れ上がった。
マールももちろん名づけに加わった。 彼女の持ち出した名前は、控えめに『ジャック』。 誰の反対も受けずに、すんなりと決まった。
-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-
ルイ王がファルツ継承戦争に明け暮れた九年間、トーメ家はいくらか寄付はしたが巻き込まれることはなく、平和に過ごした。
ジャン・ジャック・ステファーヌ・ジュリアン・フランソワ・アントワーヌ・ヴィクトル・トーメ坊やは、三歳まで一人っ子だった。 しかし、四年目から不意に弟妹が増えはじめ、やがて広い邸内は、子供たちの走り回る音で賑やかになった。
屋敷の壁には、愛らしい子供たちの肖像画が次々と掲げられた。 同じタッチの宗教画が近隣の教会や礼拝堂を飾り、セルジュ・ファベールのサイン入りの絵はどこへ行ってももてはやされるようになった。
ラリュックをファベールと改名したセルジュは、王宮推薦のアカデミー画家になったものの、一年の大半を南仏で過ごした。 有名になった後でもその行動は変わらず、特に薔薇の咲く季節には、必ずプロヴァンスにいた。
気さくで、人と話を合わせるのがうまいセルジュは、社交界で大人気だった。 しかし彼は、貴婦人たちみんなを平等に扱い、誰かと深い仲になることは決してなかった。
「うまく泳いでいくのよね。 要領がいいわ、あの画家は」
「成り上がり者の知恵よ。 世渡りをよく知っているのよ」
どう陰口をきかれようと、セルジュは平然としていた。 そのため、芸術家にしては情熱がなさすぎる、本心は冷たいのではないかといわれたりした。
そんな噂を流している連中は知らないのだ。 夏の昼下がり、リネンのシャツに革のベストという軽装で馬を下りたセルジュが、とある立派なお屋敷の中庭に入っていくと、裏の戸口から子供たちがあふれ出して、彼を取り囲むことを。
「師匠! お帰りなさい! パリは今どんなふう? 新しい大きな絵はもうできた? 流行のハンサム馬車って、どんな形?」
矢継ぎ早の質問に答え、鞄から襟飾りや手鏡、おもちゃのピストルや絵本などの土産を取り出して与えながら、セルジュの眼は一点にそそがれていた。 その視線の先には、庭の奥にある東屋に座り、魅惑的な笑顔で彼を見返している優雅な貴婦人がいた。
子供たちが満足して行ってしまうと、さっそくセルジュはマールの横に腰かける。
「お帰りなさい。 カリソン(=アーモンド菓子)はいかが?」
「ありがとう、マダム」
ふたりの指が軽く触れ合う。 ああ、また無事に会えたという喜びが、指先から指先へ脈打って流れるのだった。
うつろう愛もあるが、積み重なる愛もある。 セルジュは、マールと子供たちを生きがいにして絵に励み、トーメは、星の研究と領地の安定に心置きなくいそしんでいた。
「男を二人も幸せにしてるんだから、俺たちの妹は大したもんだよな」
久しぶりにシャルルと飲んだ夜、アンリがそう言うと、シャルルは盃をテーブルに置き、改まった口調で言い出した。
「実はわたしもそろそろ身を固めようかと思って」
アンリはあやうくブランデーを噴くところだった。
「結婚? お前が?」
シャルルはむっとなった。
「悪いか」
「いや、そういう意味じゃなく、子供の頃からやたら気が長くて、迷ってばっかりいたからさ。 よく覚悟を決められたな」
「情熱に背中を押されたんだよ」
うわー。 目も当てられないという表情で、アンリは酒を飲み干した。
「それで? 俺に相談するということは、親父殿に受け入れてもらえそうにない相手だってことだな」
「……うん」
アンリは大口あいて笑った。
「面白い! 二人で作戦を練ろうぜ。 子供のときみたいにな。 もう一軒はしごするか」
「ああ、そうしよう」
すらりとした長身と、ずんぐりした中背の兄弟は、仲よく肩を組んで、嬌声の響く夜の街へ消えていった。
【完】
このボタンを押してね →
背景:CoolMoon
Copyright © jiris.All Rights Reserved