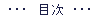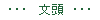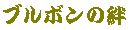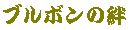

−6−
一方、広い屋敷の奥にある書斎では、アンリが椅子に片足をかけて、父親と話し合っていた。
「ですからね、平民がめったに行かないテュイルリーの話を、それも中年男たちが薔薇の色がどうのなんて話をするのは、どう考えても奇妙ですよ」
「奇妙どころじゃない」
大貴族には珍しいほど質素な無地のガウンをまとって、がっしりした胴に帯で結びながら、フランソワはきっぱりと言った。
「明らかに怪しい。 よく気付いたな。 おまえとしてはよくやった」
後半は余計だ、と思いながらも、滅多に褒めない父が認めてくれたので、アンリは自分でも意外なほど嬉しかった。
「どうでしょう。 泥棒の相談でしょうか」
「かもしれん。 だが、もっと大ごとのような気もする。 なにしろ、合言葉がキザだ。 教育のないこそ泥が考えつくようなものじゃないからな」
「そうですね」
髭をひねりながら、フランソワは大机を一周回った。
「まず考えられるのは、スパイだ」
「どこの?」
「イギリス、ネーデルラント、オーストリア、ひょっとするとロシアかもしれん」
「今のところどことも戦ってませんが」
「確かにな。 だが、頑固なカトリックで誇大妄想のルイが、ひょっと戦争を始めないという保証はどこにもない」
「父上!」
あわてて、アンリはカーテンの後ろを覗きに行った。 ルイ十四世は大貴族の家に必ず密告者を忍び込ませているという。 子供のころ、フロンドの乱で反逆された恨みが忘れられなくて、貴族と名のつく者はまったく信用しないのだった。
「びくびくするな。 あの男は最近、私を飼い慣らしたつもりでいる。 確かに謀反を企む気はないし、まして王座を狙うなどという面倒なことをやるつもりはさらさらない。 だからせめて本音ぐらい言わせてもらうさ」
「それにしても、何の合言葉でしょうね? もしスパイ以外だとすると」
アンリは急いで話を戻した。 まだルイ帝王の逆鱗に触れてバスティーユに入れられたくはない。
「うーん…… 誰かの暗殺とか」
ありうる。 財務大臣のコルベールは何度も命を狙われたそうだ。
「父上は大丈夫でしょうね?」
「わたしか?」
考えるときはいつも歩きまわるフランソワは、立ち止まって笑い出した。
「この無粋な男を殺す計画の合言葉が、テュイルリーの薔薇か? それはないだろう」
「アジトがこの近所なので、つい心配で」
「よし、明日その場所に案内しろ。 まだ連隊に戻らなくていいんだろう?」
「ええ、三、四日は暇ですが」
そのとき、ノックの音がした。 父と子は緊張して、扉に顔を向けた。
「誰だ?」
「私よ。 何で鍵かけてるの。 いかがわしい相談?」
間違いなくエレの声だったので、フランソワは肩の力を抜いた。
「あけてやれ」
「はい」
アンリが扉を開くと、ナイトガウンを着たエレが突風のように入ってきた。
背景:CoolMoon
Copyright © jiris.All Rights Reserved