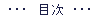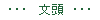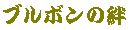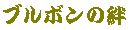

−4−
およそ一時間後、兄弟はほろ酔い加減で酒場を出てきた。
「たしかに料理はうまいし、酒も値段のわりには後口がいい」
「それじゃわたしはいったん本家の馬屋に戻って、馬車で帰るよ。 兄さんはどうする?」
アンリはちょっと考えた。
「そうだな。 今夜は暇だから、もう少し歩き回ってみるか」
「足を引きずった画家とやらを見かけたら、ルポン通りのわたしの家へ来るように言っておいてくれ」
「さっきの話、本気なのか?」
「ああ、頼むよ」
ふたりは肩を叩き合って別れた。
ごちゃごちゃした街筋をのんびりと歩き、煙草屋や銀細工の店を覗きこみながら、アンリは弟の頼みごとが頭の隅に引っかかっていて、通りにうずくまる浮浪者や皿を差し出す物乞いに注意を払っていた。
やがてその耳に、気になる言葉が紛れ込んできた。
「ランプの火をもう少し細くしなさい。 もったいない」
「はい」
そこまでは大声だったのだが、次はトーンを落として、灰色のマントを着た男がランプを持つ男に囁いた。
「テュイルリーの薔薇は今何色かな?」
ランプの男は、うつむいたまま早口で答えた。
「金色がかった曙色」
マントの男が、ふっと緊張を解いた。
「よし。 さあ行こう」
若いほうの男がランプを掲げて、恰幅のいい商人風の男を案内していった。 アンリは、壁にもたれて爪を調べるふりをしながら、横目で二人が角から三番目の店に入っていくのを見届けた。
こんな下町の庶民どもが、テュイルリーの薔薇を一時間に二回も話題にする。 しかもまったくおなじ言い回しで、おなじ答えだ。
「これが合言葉でなくて何だっていうんだ」
口の中で呟くと、アンリはさりげなく角を曲がり、男たちがすべりこんでいった店の黒い扉に、短剣の先でごく小さく×をつけた。
「アリババの盗賊だな」
きっとそれに近い連中にちがいない、とアンリは推測していた。 泥棒にしては妙にしゃれた合言葉だが、おそらく大掛かりな盗賊団で、この付近の豪邸に狙いをつけているのだろう。
もしかしたら、目当てはコンデ公の邸宅かもしれない。 見張りを厳重にするように、父か母に言わなければ。
アンリは身をひるがえして、大股で屋敷に引き返していった。
その日の夜のことだった。 母の部屋でクラブサンを弾いて仲よく歌った後、もうそろそろ寝る時間だということでおやすみの挨拶をして、鼻歌を口ずさみながら二階の廊下を歩いていたマールは、自分の寝室へ入ろうとして、足を止めた。
淡雪のような白とほのかなピンクで統一された部屋は、壁にかけた四対の燭台でぼうっと照らし出され、まるで夢の国のように見えた。
それはいつものことなのだが、普段と違うものが一つだけあった。 小間使いのシルヴィーが、爪先立って衣装箪笥の隠し扉から四角い箱を取り出していた。
背景:CoolMoon
Copyright © jiris.All Rights Reserved