

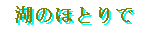 1
1

塔を巡っていく階段の途中に、小さな窓がある。 セシリアはいつものようにそこで足を止め、眼下に広がる碧色の湖を眺めた。
柔らかな風が湖面を渡り、冬がそこだけ雪を残したように細かい小波がうねった。 鴨が鳴き声を残して飛び立っていく。 その後ろ姿を見守りながら、セシリアは呟いた。
「私もあんなふうに飛んでいけたらなあ」
だが、すぐに口を閉じ、用心深く背後に目をやった。 どこで盗み聞きされているかわからない。 逃げるにも手段がないし、馬が手に入らなければすぐ掴まって連れ戻される。 叔父たちには何としてもセシリアが必要なのだった。 少なくとも、今のところは。
春になったが、その夜は肌寒かった。 一階の広間にはごうごうと薪が焚かれ、壁に炎の影が躍っていた。
セシリアは、本来ならこの城の主なのに、体よく長テーブルの端に押しやられ、叔父のアーネストと叔母のガーダがバックギャモンに興じているのを、ハンカチに刺繍しながら横目で眺めていた。
「はい、これとこれ」
「待て!」
「待てはなし。 私の勝ちよ」
また負けたのでつむじを曲げたアーネストは、乱暴に手を叩いて小姓に酒を持ってこさせた。
盃を一気に飲み干した後、アーネストは少し足をふらつかせながら、セシリアに歩み寄り、上体を傾けて話しかけた。
「どうだね? 今度はリチャード・ウィテカーが申込んできたが、身分違いもはなはだしいから、わたしから断っておいたよ。 かまわないだろうね?」
むっつりした表情で、セシリアは叔父を見上げた。 アーネストは父親のトーマスの弟にあたる人で、両親が天然痘で相次いで亡くなった後に城へやってきて住み着いてしまった。 まだ未成年だったセシリアの後見人という名目だが、亡兄の土地と財産目当てで乗り込んできたのは間違いなかった。
ゲーム台を押しやりながら、わざとらしくガーダがため息をついた。
「縁談はなかなか難しいわね。 持参金なんてかけらもないし。 モンデシャールの首飾りでも出てくれば……いったいどこに行ったのかしら」
モンデシャールの首飾り。 それはセシリアの母が嫁入りのときに持ってきたサファイアのネックレスだった。 家宝なので、どんなに困ってもそれだけは手放さなかったはずなのだが、両親が亡くなってみると宝石箱から消えていた。
叔父夫婦はもちろん首飾りのことを知っていた。 だから、城に来てから三ヶ月はあらゆるところを探し回った。
しかし、絨毯やタペストリーをすべて剥がしてまで探しまくったにもかかわらず、豪華な首飾りはどこからも発見されなかった。 今では二人ともほとんど諦めている。 兄がこっそりとユダヤ商人か何かに質入れしてしまったと思っているらしかった。
他に遺産はないに等しかった。 城は古く、絶え間ない修理を必要とした。 地代はすべて修理代と維持費に消えてしまう。 もともとセシリアは身分のわりにつましい生活をしていたが、叔父たちが来たせいでいっそう暮らしに困るようになった。
現金不足を理由にこじつけて、叔父夫婦は、もとからいた従者や雇い人たちを次々に辞めさせ、自分の部下を代わりに入れた。 だからもうセシリアには、心を開いて話せる相手がいなくなっていた。
どちらを向いてもよそ者ばかり。 現金はすべて叔父に握られている。 このまま飼い殺し状態で、虚しく青春が過ぎ去るのだろうか。 まだ十八になったばかりだが、セシリアはそろそろ焦っていた。
後一ヶ月経って、状況がよくならなかったら、覚悟を決めて逃げ出そう。 そう決めて、セシリアはこっそり準備を始めていた。 夕食のパンを少しずつ貯め、ガーダの目を盗んで古いマントから男用の半ズボンを縫い、床下に隠した。 そして最大のよりどころは、無くなったはずのあの唯一の値打ち物、モンデシャールの首飾りだった。
この首飾りは、誰にも見つからないところに隠してあった。 目立たず、それでいて必要になったらすぐに持ち出せる場所に。
翌日も穏やかな空模様だった。 こんなによい天気が続くのは珍しい。 アーネストは食料確保を兼ねて狩に出かけ、妻のガーダは聖歌隊の練習を見に行った。 ということで、セシリアは久しぶりにのびのびと城内を歩き回っていた。
裏庭には、母のキャサリンが丹精こめた薬草園があった。 そこは煉瓦の塀に囲まれ、蝶や蜂、小鳥の訪れる、城の中でもっとも美しい一画だった。
時は春。 ラヴェンダーや麝香草(じゃこうそう)の芽が伸び、ローズマリーの花が咲く時節だ。 手入れが楽しい。 うきうきと木戸を開けて足を踏み入れたセシリアは、そこで立ち止まってしまった。
中のベンチに、若者が座っていた。 青の胴着に銀色のボタンが並び、腰に下げた長剣が凛々しく決まっている。 だが、何よりセシリアを驚かせたのは、立派な服装よりも、その容貌だった。
いくらか顔を上向けて、彼はぼんやりと楡の梢を眺めていた。 まっすぐな鼻筋が緑の空間にくっきりと浮き出て、形のいい口元に続いていた。
なんて美しい横顔なんだろう――セシリアが瞬きを忘れていると、人の気配に気付いた若者が姿勢を変え、彼女と正面から向き合った。
彼は別に慌てずにゆっくり立ち上がり、胸に手を置いて一礼した。 儀礼的な声が言った。
「セシリア・フォーサイス嬢ですね。 わたしはパトリック・ウッドワードと申します」
背景:素材の小路
Copyright © jiris.All Rights Reserved

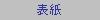
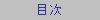
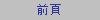



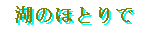 1
1




