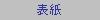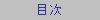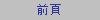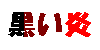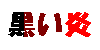 | 32 |
コニーをジェレマイアにいったん預け、二、三日中には必ず迎えに来ると確約した後、ラルフは馬でウォーレン邸へ向かった。
屋敷へ近づくにつれ、ざわざわとした落ち着かない気配が伝わってきて、ラルフの胸を嫌な予感がかすめた。
門を入って馬から下りても、普段のように馬丁が出てきて轡を取ってくれない。 広い庭の外れを二人の下男らしい男が駈けていくのが見えたが、どちらもラルフに見向きもしなかった。
仕方なく、手綱を近くの柵に引っ掛けて、ラルフはドアを叩いた。 すると、返事の代わりに泣き声が近づいてきた。
やがてドアが細く開き、眼を真っ赤にした小間使いが顔を覗かせた。 パーティーのとき下座で飲み物の用意をしていた娘で、顔だけは見知っていた。
相手もラルフを覚えていた。
「あ、バートン様」
「こんにちは、アビーだったね、君は?」
「はい」
「急ぎの用事でウォーレンさんにお目にかかりたいのだが」
アビーは涙を拭い、切れ切れに答えた。
「あの……お館さまは……ジョージさまは、お亡くなりに……」
バートンは息を呑んだ。
「亡くなった?」
「はい」
「殺されたのか?」
ぎょっとして、アビーは後ずさりした。
「いいえ、あの」
声に出さずに、口だけが動いた。
(自殺されました)
一呼吸置いた後、ラルフはできるだけ気を静めて穏やかに尋ねた。
「拳銃で?」
アビーの視線が床に落ちた。
「……はい、頭を」
「アビー、誰と話しているの?」
慌てた声が玄関の奥から響いてきた。 アビーが急いで廊下に逃げていったので、これ幸いとラルフは玄関に踏み込み、小走りに出てきたウォーレン夫人と向き合った。
「遺書は?」
単刀直入に訊かれて、夫人は顔色を失った。
「まあ、アビーったら口の軽い!」
「長いこと隠してはおけませんよ。 小さな村ですから」
するりと勝手知った屋敷に入っていくラルフを、夫人は必死に追った。
「待ってください! 許しもなしに」
「奥様ひとりの手には負えませんよ。 できるだけ穏便にすませるお手伝いをします。 ご主人はどちらに?」
ラルフの魅力は、ここでも健在だった。 裏の事情を何も知らないらしい夫人は、心細くてたまらなかったので、気さくで世知にたけた青年の申し出に、一もニもなく応じてしまった。
Copyright © jiris.All Rights Reserved