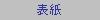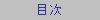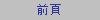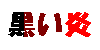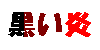 | 18 |
馬車の支度ができて乗り込む頃には、風は一段と強くなり、低い唸りを立てて道を吹き抜けていた。
「これは一荒れ来そうだ。 ウォーレンさんも間の悪い日にパーティーを開いたものだ」
コートのボタンを口のそばまでぴっちり止めて、アシュダウンがぼやいた。 一方、ラルフは生き生きした表情で楽しそうだった。
「もうじきハローウィンですからね。 丘のほうから箒に乗った魔女が飛んできそうじゃないですか」
「やめてくれ」
アシュダウンは顔をしかめて手を振った。
道中、ハーミアは一言も口をきかなかった。 まだ六時前だというのに外は真っ暗だ。 空を黒雲が覆っているので月がなく、馬車の中は弱いランプの光が照らすだけで、辛うじてお互いの顔が見分けられる程度だった。
幸い、ウォーレンの屋敷は馬で十五分ほどの距離で、馬車でも二十分とかからなかった。 玄関から広間へ通されると、二つの暖炉にごうごうと薪が燃え、肉の焼ける匂いに混じって丁子や胡椒の香りがただよい、一同はほっとする雰囲気に包まれた。
召使にコートを渡して、アシュダウンは奥から迎えに出てきた主人のウォーレンと挨拶を交わした。
「お招きありがとうございます。 外は冬のようですが、ここはすでに春ですなあ」
「さあさあ、まずはこちらに腰かけておくつろぎください。 気のおけない地元風のパーティーにしました。 食べて飲んで、それから大いに踊ったり歌ったりいたしましょう!」
農民の結婚披露宴みたいだな、と、丈夫な歯で鶏の腿肉を噛み切りながら、ラルフは思った。 ウォーレン自身も、地主というより昔ながらの庄屋という人柄だ。 素朴で垢抜けしていない。 だからかえって、気がおけなくて楽しいパーティーになっていた。
まだ食事が終わっていないのに、もうハーミアは若い男性たちに遠巻きにされていた。 その中に知った顔を見つけて、ラルフは苦笑した。
「あの坊やだ。 たしかレイモンドとか言ったが」
「え?」
横で煮込み料理に舌鼓を打っていたアシュダウンが聞き返してきたので、ラルフは少し大きい声で繰り返した。
「たしかカーク・レイモンドとか言いましたな、あの青年は」
目を細めて長い部屋のかなたを見渡して、アシュダウンはうなずいた。
「わたしの靴下を汚した礼儀知らずだ。 いかにも今時の若い者で」
「小判鮫のようにハーミア嬢につきまとっている。 今にも話しかけそうだ」
「気がかりですか?」
思いがけず、アシュダウンがウィンクしてきた。 ラルフは笑って否定しようとしたが、あることに思い当たって気を変えた。
「少しね。 行って注意してきましょう」
ハーミアは澄ました顔で食事を取っていたが、内心はざわざわした空気を楽しんでいた。 土地で中流以上の人はほとんど招かれているらしく、長方形の広間はごった返していた。 顔見知りの若者たちもちらほらといる。 彼らが守ってくれるだろうから、ハーミアが食べ終わったらダンスに誘おうとうずうずしている連中が列を作っていても、いつもほど気にならなかった。
食事の間中、暖炉のへりに陣取った楽団は押えた音量でセレナーデを奏でていた。 やがて、そろそろ頃合だと判断したらしく、いきなり陽気なメヌエットを弾き出した。 当時の舞曲は今とは違い、驚くほどテンポが速く、さっそく娘たちに申込んで踊り出した青年たちは、外の風に負けないスピードで床を踏み鳴らして踊りまわった。
また出そうになったゲップを押しころして、アシュダウンは椅子に寄りかかり、ユーナ夫人につぶやきかけた。
「いやはや、若さはいいですな。 こちらは一休みしないと、とてもあんなに飛び回れません」
夫人は答えず、ハーミアの動きを目で追っていた。 椅子から静かに立ち上がったとたん、三人の青年に囲まれてしまって、身動きが取れないでいる。 その三人に見覚えがある気がして、ユーナは眉をひそめた。
青年たちは素早くハーミアの回りに垣を作り、ライバルを近づけまいとしている様子だった。 娘を救い出そうとユーナが立ち上がりかけたとき、ラルフが一足先にさりげない仕草で三人に割って入った。
Copyright © jiris.All Rights Reserved