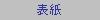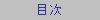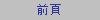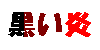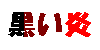 | 11 |
四人は食堂の端、暖炉に近いテーブルに陣取り、牛のシチューとうずらのスープ、ブラマンジェを注文した。
ユーナはまだ食欲がわかないようだったが、男連中はたっぷりと詰め込んだ。 ハーミアも元気に食べていた。 そしてカークは、彼女がよく見える場所に席を取り、本当に穴があくんじゃないかと思うほど見つめ続けていた。
一行が食べ終わる頃には、通常の昼食時は過ぎていて、食堂はだいぶ空いてきていた。 それでもカークは、もう帰ろうとする友達の誘いを振り切って粘り、ハーミアたちが馬車に乗って旅を再開すると、後ろから見え隠れについてきた。
「あの若者は、お嬢さんの魅力にノックアウトされたようですよ。 もう三回道を曲がったが、そのたびに馬の黒い鼻面が見えましたから」
愉快そうにラルフがユーナに話しかけると、ユーナは顔をしかめて窓から道をうかがった。
「お二方に来ていただいてよかったわ。 この子はロンドンでもバースでも、鼓笛手みたいに若い男性を引き連れて歩く羽目になるの」
ラルフは思わず笑い出した。
「それでは宮中のパーティーには行かないほうがいいですよ。 皇太子のジョージ殿も、弟君のヨーク公フレデリック殿も、美しい女性には片っ端から声をかけて回るそうです」
「困った方々ね」
ユーナは深く嘆息した。 現国王のジョージ三世は大変な愛妻家で、王妃との間に九男六女をもうけたのだが、なぜか息子たちは遊び好きな不良ばかりだった。
やがて海が見えるより先に、潮の香りが流れてきた。 馬車は砂利道に苦戦しながらも、無事に『潮風邸』の玄関先にたどり着いた。
中から、前もって館の準備に来ていた召使たちが出てきて、荷物を運び入れた。
ラルフは先に下りて、ユーナ夫人とハーミアの手を取り、次々と助け下ろした。
「まあ、どうも。 気を使っていただいて」
ユーナは愛想よく礼を言ったが、ハーミアは口の中で一言つぶやいただけでさっと手を離し、小走りで家の中へ入っていった。
ラルフはさりげなく周囲を見渡して、遠くで馬上からこちらを覗き見ているカークを発見した。
「ここまでついてきちゃいましたよ、あの男」
隣りにたたずんでいたアシュダウンは、鼻眼鏡をずり下げて、厳しい眼差しで道の彼方を眺めた。 するとカーク青年は、急いで馬の向きを変えて戻っていった。
「若い情熱か。 いいもんだ」
ひとごとのように呟くラルフに、アシュダウンはいくらか皮肉っぽく返した。
「君だってまだ充分若いよ」
「年齢はね。 でももう青くはない、と自分では思ってますがね」
「確かに」
改めて観察すると、ラルフのこめかみには白い傷跡が走っていた。 黒くふさふさした髪には、年齢に似合わぬ白髪がちらほら混じっている。 そう言えばマスケット銃の腕前は近衛兵仲間にとどろいていたそうだ、とアシュダウンは思い出した。 美貌だし、明るくて人をそらさない性格だし、近衛のままでいれば出世は間違いなしなのに、なぜ辞めたんだろう。
空には晩秋の太陽が斜めにかかり、弱い光で懸命に大地を温めようとしていた。 そのオレンジ色の球体をちらっと見上げてから、ラルフはマントをひるがえして歩き出した。 アシュダウンも肩を並べてついてきた。
「暖炉に火は入っているかな。 流木は燃やすといい匂いがするというが」
「ウェールズの冬は凄いですよ。 朝起きると、掛け布団の上に吐いた息が凍り付いてばりばりになっているんですから」
寒さに弱いアシュダウンは身震いした。
Copyright © jiris.All Rights Reserved