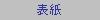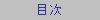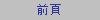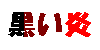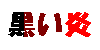 | 09 |
真っ先に意識したのは、強く迫ってくる視線の圧力だった。 自慢ではないが、ロンドンの舗道で、音楽堂や喫茶室で、じっと見つめられた経験は何度もある。 しかし、この眼差しはこれまでのと違った。 力はあるが熱がない。 憧れのしるしというより、きれいな花を観察する植物学者を連想させた。
すらっとした首を軽く動かして、ハーミアは視線を捕らえた。 それは思ったとおり、窓の外で陽気に口笛を吹いていた青年のものだった。
眼が合うと、彼はにこっとした。
気ぜわしい口調で、ユーナが紹介した。
「娘のハーミアです。 ハーミア、アシュダウンさんは知っているわね。 こちらはバートンさん。 ランカシャーの立派なお家の息子さんよ」
「八人兄弟の四番目です。 つまり、どうでもいい存在で」
ラルフはこともなげに言った。 ハーミアは儀礼的に答えた。
「大家族で栄えてらっしゃるんですね」
「集まるとうるさくて」
「馬車の支度が整いました、奥様」
ユーナはほっとして、ハーミアをうながして外に出た。 二人が召使の手を借りて後部座席に座ってから、男性たちは乗り心地の悪い後ろ向きに席を取った。 それが礼儀であると同時に、旅なれていないハーミアを気遣っての紳士的な態度だった。
街を出て少しすると、道はでこぼこになり、たまにひどく揺れた。 ハーミアは天井から下がった絹の持ち手をしっかり握って姿勢を保っていたが、握力の弱いユーナは次第に気分が悪くなり、口元を押さえてうつむく姿勢になった。
心配したハーミアが気付け薬を取り出したとき、ラルフが大声で言った。
「トレッドミルの駅舎だ! あそこで少し休んでいきましょう」
「そう、それがいい」
ユーナはほっとして眼をつぶった。
急ぐ旅ではないので、ユーナが奥の小部屋で休ませてもらっている間、男連中は宿の食堂でホット・ポンチを振舞われてくつろいでいた。
「どちらへ行きなさる?」
ラルフの明るい顔と向き合うと、年季の入ったブルドックのような主人の頬もほころび、気安く話しかけてきた。 カウンターの下にある横木に左足を載せ、ラルフは淡々と答えた。
「アレンマスにある友人の別荘へね。 ほら、チビのボニー(=ナポレオン)が休戦協定にサインしたから、やっと行けるんだよ」
「なるほど。 だが、あそこで何をして過ごしなさるんだね? ひなびた漁師町で、大して面白いものもないが」
「骨休め」
ラルフはくすくす笑った。
「ご婦人よけじゃないのか?」
酒が入って気が大きくなったアシュダウンが、珍しく冗談を言ってからかった。 ラルフはカウンターに背を向けて寄りかかり、スカートの裾を絞って忙しく動き回っている給仕女におしげなく微笑を送った。
「誰が避けたりするものか。 女性は天使。 老いも若きもね」
「その口のうまさが曲者だな。 しかも、酔って羽目を外すってことがないんだから」
いくらかへべれけになりかけているアシュダウンは、うらやましそうに吐息をふっとついた。
ちょうど昼時で、食堂はカンタベリーへ行く巡礼や近隣の農夫たちでにぎわっていた。 だんご鼻の若者が嬉しそうに骨つきあばら肉をかじり取るのを見て、ラルフの口に唾がたまってきた。
「ご婦人たちはもう落ち着かれたかな。 そろそろ昼食に……」
パタンと戸の閉まる音がして、丸椅子に浅く腰かけたアシュダウンのすぐ横を、つむじ風のように若い男がすり抜けていった。
実際、尖った靴先がアシュダウンの足をかすめたぐらいだった。 ベージュの長靴下に黒い筋ができて、アシュダウンは顔をしかめた。
威厳たっぷりのおじさんがこれ見よがしに靴下を叩いているのに気付かず、入ってきた青年は澄んだ声で、奥にたむろしている仲間らしい二人組に呼びかけた。
「ディッキーがいいってよ! プルーデンスを出走させても!」
男たちはどよめき、テーブルを離れてこちらへやってきて、青年の肩を、でかした! というように叩きまくった。
「すごいじゃないか! あれなら本命中の本命だ。 この場で2ギニー賭けてもいい」
「たったの?」
バカにしたように呟くと、青年は指先をくるくるっとひねって硬貨を空中に飛ばした。 宿の主人はさっと手を伸ばし、上手にすくい取った。
「話、聞いたろ?」
「はい」
主人はにやりとした。 馬の名前なんて知らないが、金を落としてくれるなら何でもいい。 さっそく台の下から取っておきのワインを取り出して、なみなみとついだ。 忘れられた形になったラルフは、アシュダウンに機嫌のいい目配せをくれて、お代わりを注文した。
Copyright © jiris.All Rights Reserved