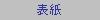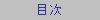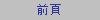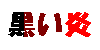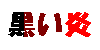 | 08 |
出発時間が迫ってきたので、面倒な儀礼は抜きで、ユーナは玄関先に出て男たちを出迎えた。
「こんにちは、アシュダウンさん、それにバートンさんも。 きちんとしていらっしゃるのね。 もうそろそろ出発しようかと準備を終わったところでしたのよ」
「お久しぶりです」
アシュダウンが四角張った礼をする横で、ラルフは人懐っこく微笑を浮かべながら近づき、帽子を取った。
「こんにちは、奥様。 あいかわらずお美しい」
首筋でひとつに結んだ黒い髪が、午後の穏やかな日に照らされて暖かそうに光った。 これから埃の舞い込む馬車に乗るというのに、鮮やかなターコイズブルーのベストが目立つので、ユーナは軽く眉を上げて皮肉を言った。
「まるでこれからダービーに出かけるような服装ですのね」
「あ、これ?」
青年は無邪気に笑った。 白い前歯が憎らしいほど清潔に見えた。
「ボー・ブランメルに選んでもらったんですよ。 彼はロンドン一の洒落者で、流行の中心なんです」
社交界の中心はあなたじゃないの? とユーナ夫人は密かに思った。 ラルフ・バートンは爵位こそないが、ランカシャー地方の名家出身で、『勇敢なバートン一族』の中でも特に知られたバートン四兄弟の次男坊だった。
「馬を飛ばしてお疲れでしょう。 荷物を積み終えるまで、テラスでお茶でも?」
「いや、そんなお気遣いは……」
アシュダウンが遠慮しようとしたのに構わず、ラルフはすぐに受けてしまった。
「それはありがたい。 いただきます」
おそらくラルフの目当てだっただろうハーミアは、お茶の席には出てこなかった。 ユーナ夫人も呼ぶ様子がないのを、アシュダウンはそっと観察して内心面白がっていた。
――ラルフと親しくさせたくないんだな。 まあ無理はない。 婚約破棄一回、婚約寸前三回、恋の噂にいたっては両手でも足りない数なんだから――
だからといって、ラルフには乱れた雰囲気はなかった。 二十五を過ぎているはずだが、光線の加減によっては十代の終わりに見えるほどの若々しさだ。 漆黒の奥深い眼で見つめられると胸をかきむしられるようになって、思わず腕に倒れかかりたくなると評判の、爽やかな美男子だった。
身支度を終えたハーミアは、広間の後部ドアから裏庭に出て、秋の薔薇が咲きにおう庭園に入っていった。
レンガの塀で囲まれた庭の一角に、1フィートほどの石碑が頭を出していた。 ハーミアはその前にひざまずき、手折ってきた白いつぼみをそっと置いた。
そよ風にまぎれるほどのささやきが、石碑を包んだ。
「メラニー、しばらく行ってくるわ。 あなたもよく知っているアレンマスの別荘に。
忠実な犬の魂で、見守っていてね。 生涯の謎が解けますように。 そして、無事にまたこの館に戻ってこられますように」
それは、彼女が『ハーミア・チルフォード』になった日から、誰に教わらなくてもベッドの足元に寝て、小さな姉のように庇ってくれた愛犬の墓だった。 黒い小犬のメラニーが老衰で世を去って既に三年が経つが、今でもふとした折に、ハーミアは彼女の手触りや、かわいい鳴き声を思い出すのだった。
墓石にそっと手を触れた後、ハーミアは長いコートの裾を軽く持ち上げて小道をたどった。 広間に帰りついたとき、ちょうどお茶の時間が終わり、話し声が近づいてきた。
「ええ、いつも夏に行っていたけれど、秋も風情があるんしゃないかって主人も言うので」
「ロントンより暖かいですしね。 人情もあつい」
「エビがおいしいそうですね」
このちょっとピント外れの言葉は、アシュダウンだった。 ハーミアはコートの裾をおろし、背筋をまっすぐにして、人々が入ってくるのを見守った。
Copyright © jiris.All Rights Reserved