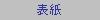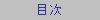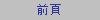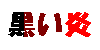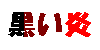 | 05 |
チルフォード夫妻は相談して、しばらくバースにある別宅へ行くことにした。 気候の温暖な保養地だし、海から離れていて少女に辛い思い出をよみがえらせることがない。 のんびりとした空気の中で、イギリスになじませたかった。
少女は相変わらず過去を語らなかった。 それで夫妻は新しく、彼女にハーミアという名前をつけた。 ハリエットにできるだけ似た響きにしたかったのだ。
英語を教えるのはキースの役目だった。 ユーナはいそいそと、屋根裏部屋にしまいこんでいたハリエットの童話本を出してきて、新しい『娘』の教材にした。 ハーミアは集中力のある性格で、新しい父の発音に注意深く耳を傾け、何度も繰り返してひとつひとつ覚えていった。
一家にとって平和で穏やかな七年間が過ぎた。 ハーミアは丈夫な体質で病気ひとつせず、春を迎えるごとに美しさを増していった。 十二歳ごろから、道を歩くと人が振り返って見るようになり、十四歳になると、教会の行き帰りにこっそり後をついてくる若い男性まで現れて、六月からはキースが馬車で娘の送り迎えをしていた。
軽快な四輪馬車で、木漏れ日の中を進みながら、キースは横の娘にぼやいた。
「あまり早く大人にならないでくれよ。 近所の十四の子はみんなクリスマス・クッキーみたいに子供っぽくて、輪回しや棒キャンディーが似合う顔をしているのに、おまえはもう一人前の淑女だ。 この界隈でなんて呼ばれているか知っているかい? 『小さな貴婦人』だそうだよ」
ハーミアは眼を伏せて微笑んだ。 まだ化粧を知らない頬は淡い桜色に透き通り、白い額は皺ひとつなく滑らかに輝いていた。
娘を庇うように横へぴったりと座ったユーナが、代わりに言い返した。
「この子は大人びた振る舞いなんかしていないわ。 普通に動いていても優雅に見えるだけよ」
「それはそうなんだが」
キースは溜め息をついた。
「この年でもう二件も求婚されるとなると」
「ロンドンはせせこましくて、人目が多いから」
ユーナ夫人も吐息を漏らした。 夫妻は視線を取り交わし、キースのほうが咳払いして口を切った。
「あのな、ハーミア。 新しく別荘を買おうと思うんだ。 スコットランド辺りでどうかな」
ハーミアの眼が上がった。
「アレンマスの『潮風邸』は?」
はっとして、キースの手がステッキの握りを固く掴んだ。 まさか娘の口からその名前が出るとは思わなかったのだ。
「あそこにはもう七年も行っていないな。 いろいろ思い出して辛いだろう? いっそのこと売ってしまおうかと考えているんだが」
「できれば行ってみたいの」
囁くように、ハーミアは言った。
「お墓参りもしたいし。 もしお父様とお母様が許してくれたらだけど」
思いがけない言葉に、夫妻は痛いところを突かれた表情になった。 ハーミアの実の家族が眠っているアレンマスの墓地。 そこに建てられた粗末な墓標を、夫妻はハーミアに思い出させまいと、これまで固く口をつぐんでいた。 悲しませたくないという思いやりと共に、早く忘れてほしいという利己的な気持ちがあったことは否定できない。 もはやハーミアは、夫妻にとってハリエット以上に大事な我が子だった。
ハーミアの手をそっと握って、ユーナは尋ねた。
「海や崖を見ても、気分が悪くならない?」
「ええ、はっきり覚えていないから」
柔らかい声で答えたハーミアは、母の細い手を静かに握り返した。
その年の夏、チルフォード一家は久しぶりにアレンマスの別荘に向かった。
キースは仕事でロンドンと往復を繰り返し、始終留守にしていた。 そして足の弱いユーナは少し歩くと疲れてしまい、あまり遠くへ行かなければとの条件付きで、ハーミアの単独行動を許してくれた。
小さな村はのどかで、都会に比べれば遥かに安全だった。 ハーミアは白い砂地の広がる海岸の散歩を楽しみ、地元の漁師や流木拾いの子供たちに気さくに話しかけて、気取らないかわいいお嬢さんとして人気者になった。
ひなびたこの地方で、ハーミアの美しさはいっそう輝きを増した。 幼い日には顔の周りに縮れていた髪は、ブラッシングの手入れによってゆるやかな巻き毛となって首筋を覆い、まるで黄金の滝のようだと女たちをうらやましがらせた。
彼女が流れついた日のことを覚えている村人も多く、仲よくなると本人に話してきかせた。
「ほれ、あそこ、あの岩の隙間に、嬢ちゃんは挟まっていなすったんだ。 今なら無理だが、あんときゃ小っこかったからな」
ハーミアは背中に髪を跳ね上げ、泉のような青い眼を細めて、切り立った崖を見た。
「あんな狭いところに?」
「そうなんだ。 死んじまってるんじゃないかって、助けたワットも心配したらしい」
「お礼を言わなくちゃ」
ハーミアが真面目な口調で言うと、話した漁師ゴーディー・ラッセルは咳払いし、手に持った手網〔たも〕をこねくり回した。
「そりゃできねえ相談だ。 ワットは死んじまったからな」
驚いて、ハーミアは目を大きく見開いた。
「死んだ? どうして?」
「事故さ」
残念そうに、ゴーディーは呟いた。
「いい奴だったが。 タラが大漁だってんで喜んで、パブでみんなにおごった帰り道に、足すべらせてペンドマーの小川に落ちたんだ。 それほど酔ってるようにも見えなかったんだがな」
ハーミアは唇を噛んで、海の彼方を見つめた。 よく晴れて空気の乾燥した昼下がりで、対岸の大陸がかすかな紫色の筋となって揺れていた。
Copyright © jiris.All Rights Reserved