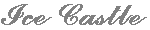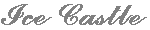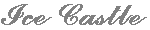 | ―氷の城―11 |
淡い夢のような時間は一日中続いた。 また一人分だけ運ばれてきた食事を取った後、頬に傷のある男が部屋に来て、うやうやしくこう言った。
「町を見物なさりたいそうですね。 わたくし、ジャレッド・ハーコートがご案内します」
彼が手を叩くと、後ろから二人の小姓がすべりこんできて、緑色のビロードのドレス、毛皮のマントとお揃いの帽子を、次々とアストリッドの前に並べた。
城の裏手には、すでに馬が用意されていた。 ジャレッドとその供の者に連れられて、アストリッドは緩やかに下る坂道を降り、寒さに身をすくめて寄り添う店々へと向かった。
品物を指差せば何でも持ってまいります、とジャレッドは言った。 望み放題、買い放題ということだ。 目を輝かせて生地屋、靴屋、小間物屋と回ってみたものの、目移りした上に疲れてしまって、結局柔らかなセーム革の手袋とヴェールを買い、服を一着注文しただけだった。
それでも帰り道は心が満ち足りていた。 町を見物したいというのは、ひとり残る口実にすぎなかったが、城主は初日からアストリッドの望みを気にかけ、お付きまでつけて叶えてくれたのだ。 大事にされるのはいい気持ちだった。
雲に乗ったような一週間が過ぎた。 その間、二度城主は秘密の扉から訪れ、明け方になる前に姿を消した。 アストリッドは熱い彼の体に腕を回して抱きしめるのが好きだった。 あまりに熱すぎるのではないかと気がかりだったが。
発熱しているのではないか、とアストリッドは心配していた。 火傷は深いと治りが遅い。 どんな顔になっていても驚かないから、看病させてほしいと思うのだった。
だが、城主はかたくなにマスクを取らなかった。 部屋を明るくすることも拒んだ。 そのため、彼と過ごす夜のひとときは、妖精が運んできた魔法の時間のように現実感がなかった。
八日過ぎると、アストリッドは新しい生活に慣れ、次第に退屈を感じはじめた。 塔の部屋は広く静かで居心地がよいが、人の出入りがほとんどなくて寂しかった。 ひとりだけで食べると、いくらご馳走でも食欲が落ちる。 なぜ下の大食堂に行ってはいけないんだろう。
刺繍の道具をケイティに取りに行かせた後、窓に寄って緞帳を脇によけ、鎧戸を開くと、昨夜からの雪は小降りになって、弱い風に散らされていた。 中庭は一面銀色に染まり、ひっそりと静まりかえっている。 その中を、黒いマントに身を包んだ男が一人、右から左へ横切っていった。
男はフードを後ろへ流し、頭を見せていた。 茶色の髪と高い鼻に見覚えがある気がして、アストリッドは眉を寄せて思い出そうとした。
窓枠に載せた手を頬に当てようとしたとき、手首が枠石に引っかかって腕輪の留め金が外れた。 あっと指を伸ばしたが間に合わず、丸い腕輪はちらちらと光りながら積もった雪目がけて落ちていった。
背景:b-cures
Copyright © jiris.All Rights Reserved