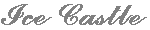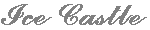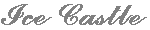 | ―氷の城―10 |
やがて城主もするりとガウンを脱ぎ、上掛けを剥いでベッドに横たわった。 厚い胸板の下で筋肉が波打っている。 じかにその胸に抱きしめられ、アストリッドは海原をただようかもめのように激しく揺らいだ。
やがて安らぎが訪れた。 薪の燃える小さな音を子守唄に、アストリッドは城主の腕で目を閉じた。
耳元に柔らかい息が連なった。
「お寝み。 すべてをわたしに任せて。 しばらく待ってくれたら、必ず……そう、必ずわたしは……」
後は聞き取れなかった。 男の声が消えたのか、アストリッドの意識が遠のいたのか、定かではない。
明け方は一段と冷えた。 足先が氷のようになったので、アストリッドは体を丸めるようにして、うっすらと瞼を開いた。
横には誰もいなかった。 暖炉の火も消えかけている。 大家族の末娘で何でも自分でできるようしつけられたアストリッドは、小間使いを起こすまでもなく、上掛けを体に巻きつけてベッドから降り、ほだ木をつぎ足して火を作り直した。
そのまま屈みこんで火に当たっていると、昨夜のことが夢のように思えてきた。 全身に黒をまとった影は、夜の帳〔とばり〕が姿を変えた幻だったのではないか。 本当に自分は城主ユージン・デクスターの想い人になったのか。 あの賢く頼もしい老将軍の……?
薄闇で触れた背中の温かさが、不意に強くよみがえった。 あれは確かに現世の体。 はかなく朝露に変わる幻影ではなかった。 彼の肌にはところどころ傷があり、ささくれて指にかかった。
細かく思い出すごとに、誇りが胸を大きくふくらませた。 強い男は魅力的だ。 彼は、城主という肩書きを取り払っても、勇敢で頼もしい戦士だった。
記憶をたどって、アストリッドは壁に行き、継ぎ目のあたりを押してみた。 壁は動かなかった。 裏から留めてあるらしい。 どこへ通じているのだろう。 いつか教えてもらおうと、アストリッドは心に決めた。
やがて小間使いのケイティが入ってきて、女主人が暖炉の前に座りこんでいるのを発見してあわてて駆け寄った。
「申し訳ございません! まだお目覚めではないかと」
「いいのよ」
すっかり温まったアストリッドは歯を見せて笑い、両腕を大きく広げた。
「ああ、なんだかおなかが空いたわ。 いい朝ね!」
背景:b-cures
Copyright © jiris.All Rights Reserved