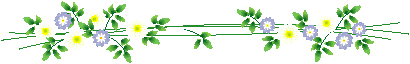
1時21分、ぜいぜいと息をつきながら、レンフィールド卿は書斎に飛び込み、脚立を持って、西側の壁一面を埋めた本棚に歩み寄った。 そして足元に注意しながら脚立に上り、上から二番目の棚に触れて、灰色の背表紙の分厚い本を取り出した。
本の中身は四角く切り取ってあった。 中にすっぽりはめ込まれた小箱の蓋を開けると、レンフィールドは心からほっとして、肩を大きく上下させた。
「無事だ」
そうつぶやいたとき、また廊下の端からただならぬ怒鳴り合いが響いてきた。
「だから確かに切ったんですよ。 絶対に怪我、それも大怪我をしてるはずなんです!」
「部屋は埃と足跡で乱れているだけ。 どこにも血の跡なんかないじゃない。 そもそもあの部屋はもう何年も使ってないのよ。 家具だってずっと布をかけっぱなしだし」
「信じてくださいよ、叔母さん!」
二人の大声に足音が入り乱れてこっちに近づいてくる。 また言いつけに来るつもりだと知って、レンフィールドは急いで本を戻し、苦虫を噛み潰した顔で脚立を降りた。
床に足がつくかつかないかで、けたたましい叫び声が下のほうから上がってきて、夜の空気を引き裂いた。
「血だ! 神さま、血だらけだ!」
廊下を歩いてきていたヘンリーとマグダ、書斎で脚立の横にいたレンフィールド、その三人がいっせいに階段めがけて走った。
騒ぎの出所は厨房、それも午前中、三角関係のもつれで若者たちが対立した、あの出入り口の付近だった。 人々が出入りのたびにすり減らして石の床がへこんでいる当たりに、まさに血だまりといっていい状態で赤黒い大きなしみができていた。
ヘンリーは若さにまかせて真っ先に台所にたどりついたが、その血を一目見て気分が悪くなって後ずさりし、居間に撤退してしまった。 後から入ったレンフィールドもたじたじとなり、頭を掻いて立ち尽くした。
「これは……」
おそるおそる夫の横から覗きながら、マグダがささやいた。
「ヘンリーの言ったこと、嘘じゃなかったのね。 怪盗ゲイルは怪我をしてるんだわ。 それも相当ひどい状態。 こんなに血が出たら、とても立ってはいられないわね」
料理番のドドソン夫人が、走ってきたメアリと手を取り合って廊下でふるえていた。 どちらも白い寝巻きを着て、同じく白いナイトキャップをかぶっている。 青ざめたメアリをしっかりとした腕でかばいながら、ドドソン夫人は憤慨した。
「なんてありさまでしょうね、これは! 私は仕事柄よく鳥や豚をさばくけど、メアリは子供に毛が生えた年で、血なんか見慣れてないんだから、かわいそうですよ、本当に!」
「大丈夫です。 ドドソンさんは寝ていて。 私が掃除するから」
そう言いながらも、メアリは可憐な顔をそむけて現場を見ないようにしていた。
下男のマックが重い足音をさせながら庭から入ってきて、強いなまりのある声で言った。
「オレが片づけとく。 あんたこそ寝な。 明日は早くから教会へ行くんだろ?」
そういえば、明日は、というより、もうすでに日曜日だった。
ヘンリーが居間で椅子に倒れ込み、頭を抱えていると、そっと肩に手が載せられた。 神経過敏になっていたので、ヘンリーは文字通り飛び上がった。
「あ、失礼。驚かせてしまったらしいですね」
それは、さっき庭から姿を消していた牧師のラーキンだった。 ラーキンは台所にちらっと視線を走らせると、椅子を引いてヘンリーの横に座った。
「今までグレイさんの相手をしていたんですよ。 庭にいたら腕を引かれましてね。 どうしても告白したいことがあるというんです。 それで、今まで話が長引いてしまいました」
ヘンリーは上の空でうなずいた。 ジェニファーの世話係のグレイ夫人は女主人に似て、無口で何を考えているのかわからない中年女性だ。 さして興味は持てなかった。
賢そうな眼で、ラーキンはヘンリーの放心した表情を読もうとしていた。
「血が嫌いなんですね」
「嫌い… ええ、がまんできないんです。 臆病だと自分でも思うんだけど」
ヘンリーはまた腕に顔を埋め、声がこもった。
「軍隊に入ってボニーと闘いたかった。 祖国を守りたかったんです。 でもこの状態では、使い物にならない。 くやしいです。 みじめだ!」
「自分をそう責めないで」
ラーキンは優しく言った。
「事情があるんでしょう? よかったら話してみませんか」
ヘンリーはゆっくり頭を上げ、かすれた声でつぶやいた。
「そう…ですね。 話すなら、牧師さんが一番だ。
見てしまったんです。 12のとき、まだ声変わりもしてない子供のとき、母が血の海の中に倒れているのを」
ラーキンは静かに呼吸していた。
「それで?」
「父は20代で結核で死に、母は未亡人でした。 子供は僕だけで、まだ若い母には再婚の話が出ていたそうです。 でも親戚たちは反対していました。 母の財産が他の男のものになるのが嫌だったんでしょう。 まあ、当然の心理ですね。
母はたしかに子供が見てもきれいな人で、服は一度着たら二度と手を通さないし、宝石もしょっちゅう買って、始終デザインを変えて作り直させていました。 上流夫人の贅沢ですね。 うちには年中宝石商が出入りしていました。 それで女子供しかいないんだから、泥棒にとってはよだれの出るような獲物だったでしょう。
盗みに入ったのは若い銀行員です。 といってももう結婚していて、こどもが2人いました。 初めから母を殺す気はなかったと思います。 盗んでいる現場を発見されて居直ったのでしょう」
「その銀行員はどうなりました?」
ヘンリーは土気色の顔を上げた。
「逃亡しました。 たぶん植民地へ逃げたんだと言われています」
深い息をついて、ラーキンは慈しみのこもった表情でヘンリーを眺めた。
「人は苦しみを知ってはじめて強くなるといいます。 あなたは弱いんじゃない。 恐れを知ったんです」
「怖いもの知らずの日々が懐かしい」
「誰でもそうですよ」
ヘンリーは落ち着いた風情の牧師を見つめた。
「あなたでも恐れはあるんですか? たしか聴解牧師として軍に参加して2年前まで敵地深く入っていたと聞きましたが。 とても勇敢で、怪我をした味方の兵士を引きずって安全地帯まで運んだそうですね」
「まあ事実ですが、その場のはずみですよ。 恐怖を突き抜ける瞬間というのがあるんです。 あなたにもきっと訪れるでしょう。
いいですか、 自分は勇敢だ、臆病ではない、と常に心の中で唱えなさい。 物事は、自分の思ったほうに進むものです」
「そんなものですか?」
信じない口調で、ヘンリーは尋ね返した。 ラーキンは確信を持ってうなずいた。
やがて、ざわざわと音が近づいてきて、疲れた顔の人々が居間に次々と入ってきた。 レンフィールド卿、マグダ夫人、まだ手を握り合っているメアリとドドソン夫人。 そしてメアリの後ろには、忠実で誠実なアランがぴたりと付き添っていた。
メアリと共にいるアランを見て、ヘンリーの顔が引きしまった。 すらりとした、むしろきゃしゃなぐらいの体を起こすと、ヘンリーはまっすぐ立ち上がり、冷たい口調で言った。
「まさかこれまでメアリの部屋にいたわけじゃないな」
さわめきはぴたっと静まり、異様な沈黙が部屋を支配した。 アランの、たくましい体躯に似合わぬ少女のような青い眼がまたたいた。
「それはわたしよりメアリに失礼な言葉だろう」
「だが君たちは普通の仲じゃない。 そっと目を見交わしているのを何度も見た。 肩を抱いているところも。 そして今だって」
ヘンリーの声が甲高くなった。
「こっそり後ろから抱きしめているのを、僕が気付いてないとでも思うのか!」
風が妖魔のように吹き込んできて、机に置かれた燭台の火をゆらした。 不意に庭に通じるガラスの扉が開き、人が入ってきたのだ。 それは、見事な金髪を背中に流した、セイレーンのようなジェニファーだった。
なぜか男物の長いマントをまとって、ジェニファーは一同を見渡した。 まるで夜の女王のように堂々と、そしてどこか悲しげに。
澄んだよく通る声で、彼女は言った。
「私の口から真実を話す? それとも、他に語りたい人がいらっしゃる?」
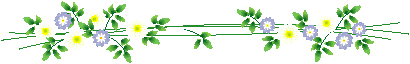
次の回で犯人と犯行の動機が明るみに出ます。 起こったことは正直に書いていますが、犯人だけは嘘をついています。 ちょっとした楽しみとして、次の3つの答えを考えてみてください。
 |  |  |  |
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
