

ローダムの町を通り過ぎるとき、リチャードは頭を上げて昂然としていたが、ジョン王子はうつむき加減だった。
結局、ハロルドとエニッド姫の言い分が認められ、リュック・ドラペーズは領地没収の上、イングランドから追放処分となった。 マルクは土地のほぼ半分を取り上げられ、ますます弱小地主となってしまった。
姫を手に入れるどころか、重傷の弟ラファエルを抱えてノルマンディーの本領地に逃げ帰らなければならなくなったリュックは、見るも哀れに落ち込んでいるという噂だった。
「ブレーズ卿をひどく恨んでいるそうだ。 あの男が余計な入れ知恵をしなければ、イングランドで羽振りのいい暮らしができたのにと」
「そう言えば、卿はどうなった? 盗賊に襲われたという話だが」
「こちらは《追いはぎジャック》に身ぐるみはがされて剣もなしにおっぽりだされたとよ。 寺侍のくせに女に手を出したりするから、天罰が当たったんだ」
面白いことの少ない田舎のことだ。 噂はしばらく渦を巻き、1週間が過ぎてもなかなか収まらなかった。
エニッド姫の人気は、この騒動で一段と上がった。 他の騎士たちがいっそう憧れて、また同じような事態になるのではないかと不安に駆られたハロルドは、息子のエドワードを説得して、リチャード王に結婚の許しをもらった。
式はひなびたアイルマーの教会ではなく、ロンドンのW大聖堂で華やかに執り行われた。 エニッドがあまりに美しかったので、教会の鳩が尖塔から見惚れて落ちたという話がまことしやかに伝わってきた。
ミリアムが分厚いヴェールをなびかせてハンコック館の前庭に入ると、井戸端で料理人と立ち話していた小間使いのリスベスが声を上げて近づいてきた。
「まあ、ミリアムさん、お久しぶり」
隠そうとしても、眼が好奇心に輝いている。 あの騒ぎでおびえた2人組、アンとエセルが相次いで故郷へ帰ってしまったので、独りになって忙しいはずだが、何かのんびりとして、気楽そうだった。
ミリアムはぎこちなく挨拶すると、若奥様に会わせてほしいと頼んだ。 リスベスはすぐに引き受け、軽い足取りで家に入っていった。
エニッドは喜んで、すぐに自室へミリアムを招き入れた。 そして、手を取ってなぐさめた。
「噂なんか気にしちゃだめよ。 みんな面白がって言ってるだけなんだから、すぐ忘れるわ」
ミリアムは無理をして微笑んだ。 最近、努力しないと笑えなくなっている。 気持ちの浮き沈みが激しく、自分でも持てあまし気味だった。
「実は、今日はお別れに来たんです」
エニッドの表情が変わった。
「お別れって、どこかへ行くの?」
「ええ」
そう言いながら、ミリアムはふところから包みを出して、エニッドに渡した。
「これは結婚のお祝いです。 受け取っていただけますか?」
淡い水色の絹を開いて、エニッドは眼を丸くした。 そこにはウズラの卵ほどもあるルビーが、真紅に輝いていた。
「これ…」
「父が私の結納の一部にと買っておいたものだそうです」
ミリアムが辛そうに言ったので、エニッドはあわてて包みを返そうとした。
「それをどうして私に?」
「もう結婚はしませんから」
「何言ってるの!」
エニッドの声が自然に大きくなった。
「あんな男のことなんか、気にする必要がどこにあるの! なんなら私が口をきいてもいい。 最高のお婿さんを見つけてあげる!」
「いえ」
小さく言って、ミリアムはルビーをエニッドの膝に置いた。
「これは姫のほうが私より絶対似合います。 アレキサンドリアから手紙を出しますね。 どうか末永くお幸せに」
それから、気にかかっていたのでそっと尋ねた。
「エドワード様は、昼も……夜も、やさしいですか?」
エニッドは、少し考えた。
「そうねえ。 悪くはないわね。 ベッドのほうが藁の上より寝心地がいいし」
たじろいで、ミリアムは立ち上がった。
「それではこれで」
「あ、エディに会っていかないの?」
「いえ」
あわてて答えると、ミリアムは早々に逃げ出した。
従者を従えて広い庭を横切りながら、ミリアムは無意識に独り言を言っていた。
「藁よりベッドが寝心地いいって、エニッド姫は結婚前に何やってたのかしら」
もう昼間でも吹く風が冷たい。 従者が気を遣ってミリアムにケープを渡した。 刺繍を襟一面にちりばめた繻子のケープを身にまとったとき、強い視線を感じて、ミリアムは肩越しに振り返った。
そこにいたのはエドワードだった。 青空を映したような瞳には、不思議な悲しみの色があった。 ミリアムは急いで顔をそむけ、従者をうながして馬に乗った。
その夜、ミリアムが寝る支度をしていると、犬が鋭く吠えた。 うさぎかキツネが庭に出てきたのだろうか。 ミリアムは何気なく窓辺に近寄った。
庭を影が動いていた。 黒い姿が音を忍ばせて、木から木へと身を隠すように移動している。 とたんにミリアムの胸が激しくうずいた。
急いで目立たない色のケープを羽織ると、ミリアムは忍び足で階段を下りた。 そして、細く扉を開いた。
庭の開けたところに出ようか出まいかと迷っていた黒い影は、ミリアムの動作に勇気づけられて、走り寄ってきた。 彼が間近まで来て、さっと頭巾をはねあげたとき、ミリアムはようやく自分の間違いを悟った。
頭巾の中にあったのは、上気した金髪の青年の顔だった。 あわてたミリアムは素早く扉を閉めようとしたが、一瞬遅く、戸口に靴の爪先をはさまれてしまった。
強くこじ開けようとしながら、エドワードは荒い息でささやきかけた。
「やはりそうか。 作戦は成功だったな。 あの巡礼と、人目を忍んで逢引きしていたんだな」
「してません!」
まんまと姑息な変装にだまされたと知って、ミリアムは頭に血が上り、ドアの下から突き出た足を思い切り踏みつけた。 エドワードはうなり声をあげた。
「やめろ! なぜそんなに嫌うんだ!」
「嫌うも何も、エドワード様は式を挙げたばかりじゃありませんか! もう他の女を追いかけるなんて、誓いの言葉が泣きますよ!」
「知ってるはずだ! 気がつかなかったとは言わせない。 わたしが本当は誰を想っているか……」
扉がみしみし言いはじめた。 家のものが不審がって起き出してくるかもしれない。 ミリアムは唇を噛み、最後の手段としてふところから短剣を出そうとした。
そのときだった。 かすかな渦巻きが起こり、エドワードはまるで藁人形のように軽々と扉から引きはがされて、庭に転がった。
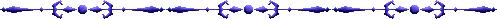
 |  |  |
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
