

リチャード王が14名のお供を引き連れて城内に入ると、階段からジョン親王が降りてきて出迎えた。
「これは兄上。 ご無事でなにより」
「あまり無事ではないがな」
リチャードは眉を寄せた。
「ごうつくばりのハインツ(ハインリッヒ6世のニックネーム)のおかげで、身代金が底なしに必要だ。 誓いを立ててようやく帰国を許されたのだが……」
眉だけでなく、口元までがきゅっと絞られた。
「いざというときの頼みの綱を、おまえたちがいたぶったというではないか」
リュックと親王は素早く目を見交わした。 どちらも当惑している。 主謀者が女と逃げてしまったから、2人とも立場がなかった。
「あれは……」
弁解しかけて、ジョンは気を変えた。 リチャード王は戻ってきたばかり。 どこまで事情を知っているか、まずそれから探らなければ。
「お疲れだろう。 二階へ上がって、何か軽く食べてからにしては」
「そうさせてもらおう」
国王はマントを小姓に投げ、せっかちな足取りで階段を駆け上がっていった。
城の地下室で頭を抱えて座っていたエドワードは、錠前がカチャッと音を立てて外れ、すんなりした姿が忍び込んできたので、急いで立ち上がった。
「エニッド!」
「シッ」
口に指を当てて、エニッド姫は足音をしのばせながら入ってきた。
「リュックのバカが、結婚してくれなきゃ首をくくるとか言ってずっと部屋の前でがんばっていて、これまで出てこられなかったのよ。 今は用を足しに行ったわ。 だからこっそりここに来たの。 こっちの見張りは手薄ね。
大丈夫だった? 何かひどいことされなかった?」
「2発殴られ、4回蹴られただけだ」
エドワードはぶすっとして答えた。 そして、息せききって尋ねた。
「ミリアムは? あの子はどうなった?」
あきれて、エニッドは口を尖らせた。
「どういうこと? 私が知るわけないじゃないの。 真っ先に部屋から連れ出されたんだから」
「そうか……」
肩を落としたエドワードを見て、エニッドは心配になった。
「ミリアムがどうかしたの?」
とたんにエドワードの顔が怒りで赤くなった。
「あいつ! よそ者の、なんとかいう大男が、ミリアムをさらっていったんだ!」
窓辺に寄りかかっていた父親のハロルドが、胴間声で言った。
「ブレーズ・ド・サンジュストだ。 テンプル騎士団の花形だよ。 前にリュックから聞いたことがある。 驚くほど強いが、残忍ではないそうだ。 戦いのない日は一日中でも祈っているとか」
「あいつが? そんな風には全然見えなかった!」
エドワードは怒鳴り散らした。
「第一、あいつは晩餐会にいたか? わたしはミリアムを引きずっていくときにちらっと見ただけだ。 エニッド、君は紹介されたか?」
エニッドは首をかしげた。
「サンジュスト? いいえ、そんな名前の騎士には会った覚えがないわ」
「どこから沸いて出たんだ、あののっぽは!」
「うるさいぞ!」
耳をふさいで、ハロルドが怒鳴り返した。
外の見張りもそう思ったらしい。 戸を開けて剣をちらつかせながらわめいた。
「おとなしくしろ! さもないと……」
どうするつもりだったのか、結局わからなかった。 ドアの裏に素早く隠れたエニッドが、そばに転がっていたワインの壷を、思い切り頭に振り下ろしたからだ。
パンを豪快にナイフで切り取って口に運んでいたリチャード王の手が、空中で止まった。 くぐもった音が廊下を近づいてくる。 やがてその音は、がやがやとした人の話し声になった。
「こちらです。 まあそうかっかなさらずに」
「怒らずにいられますか! われわれは晩餐会の招待を受けただけ。 それなのにいきなり」
ドアが勢いよく押し開けられ、まずエドワードが、それからハロルドが乗り込んできた。 その様子を見て、リチャードの横に座っていたジョン親王は、思わず目をつぶった。
ハロルドはさすがに大人の風格で、リチャードにしっかりと一礼し、それからジョン王子に向き直った。
「エニッド姫は12のときから、ここにいる我が息子のエドワードと婚約しております」
ジョン王子は苦虫を噛み潰した顔で、あさっての方角を見た。 リチャードは、対峙している弟と郷士をかわるがわる眺め、ナイフを皿に置いて尋ねた。
「どういうことだ? ハロルド殿、詳しく説明していただこう」
翌日の午後、前の通りが急に賑やかになったので、シメオンは下男に命じて様子を見に行かせた。 半時間ほどして戻ってきたベニヤミンは、呑気な口調で報告した。
「国王が戻られたそうです。 臨時のじゃなく、リチャード王様が」
びっくりして、シメオンは窓から首を突き出した。 そんなことをしても見えるはずはないのだが。
「王様は今、どこにおいでだ?」
「昨夜はラペーズ様の城に泊まって、これからアイルマーに向かうとか」
あの城に! シメオンの表情が引きしまった。 そして、大急ぎで着替えはじめた。
「そうか。 よし、わしもお供してアイルマーに行く。 行って直訴する。 娘をあんな目に遭わせた寺侍を、厳しく処分してもらう!」
「お父様」
静かに入ってきたミリアムが、元気のない声で言った。
「無駄よ。 そんなことしても」
シメオンはかっとして顔を激しく上げた。
「無駄? そんなことはない! 国王は喉から手が出るほど金が欲しいんだ。 われらを怒らせたらどうなるか、よく知っているはず」
「あの騎士は、とっくにこの土地を離れているわ」
シメオンは、まじまじと娘を見つめた。
「どうしてそんなことがわかる」
「わかるの。 訴えてもうやむやにされるだけよ。 もういないんだから。 それに……」
話しながら、頬に涙が筋を引いたので、シメオンは思わず娘の手を取った。
「忘れなさい」
ミリアムの唇がふるえた。 たった1日で細くなった気がする娘の肩を抱き寄せて、シメオンは懸命になぐさめた。
「何かあったか言わなくていい。 たしかにここではもういい縁談には恵まれないかもしれないが、他所の土地へ移ればいいんだ。 これまでも、危険になれば引っ越してきた。 なあ、ミリアム。 何も気に病むことはない」
父の誤解を解こうとはせずに、ミリアムは窓の外を眺めた。 どこか虚ろな眼の色だった。
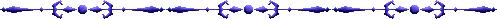
 |  |  |
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
