

青毛の馬は風を切って走った。 ブレーズ・ド・サンジュストはミリアムを鞍の前に乗せ、たくましい左腕にしっかりとかいこんで、愛馬を駆った。
月夜だった。 中空に、ほぼ球形の大きな月が浮かんでいる。 埃っぽい道筋に影が落ちるほどの明るさで、馬は迷うことなく突き進んだ。
耳元を風が殴るように吹きすぎていく。 その風にところどころ千切られながらも、男の低い声がミリアムの耳に届いた。
「お前が愛しい。 一目で……そうだ、一目見て心が宙に浮いた。 こんな気持ちになる日が来るとは、ただの一度も……」
ミリアムは眼をつぶった。 黒い馬は大きく道を曲がり、光の届かない森の中へ入っていった。
ここはどこだろう――ミリアムは懸命に意識を集中しようとした。 シェフィールド付近はなたらかな丘陵で、いくつもの森におおわれている。 夜のこんな時間では、どの森を抜けているのか見分けるのは困難だった。
この人にはわかっているのだろうか――リュック・ドラペーズの城を出てからどう走ったか、ミリアムは頭の中で道筋をたどろうとしたが、できなかった。 思い出せないのだ。 頭の中身が溶けてしまったように、ミリアムは半ば催眠状態に入っていた。
そのとき、唐突にドサッという音がして、黒馬がいななき、無理に止まろうとして竿立ちになった。
長い前足が空中をかいた。 ふり落とされかけたミリアムを、ブレーズが危うく支えた。
ほんの数秒の間に、周囲は人の気配で一杯になっていた。 やがて木陰から松明の光が1つ、また1つと近づいてきて、ようやく事情がわかった。
馬は少なくとも20人の盗賊に囲まれていた。 ここはどうやら、《追いはぎジャック》の本拠地、メイヨーの森らしかった。 シメオンが襲われた、あの現場だ。
なめし皮のような顔をしたのっぽの男が歩み出てきて、ブレーズを見上げ、決り文句を呼ばわった。
「もう逃げられないぞ。 持ち物全部置いていけ」
左手でミリアムの胴を引きよせ、右手で腰の刀を抜き払ったブレーズは、厳しくジャックを威嚇した。
「どけ! 麦穂のように首を落とされたいか」
「そりゃ何人かはやれるだろうがな」
ジャックはのんびり答えた。
「この人数を見ろ。 きさまがそのなまくらを振り回している間に一斉に飛びかかれば、八つ裂きにだってできるんだ」
周りを固める荒くれ者だけでなく、木の間からさらに子分たちが集まってきていた。 総勢40人近く。 戦争と酷税、その他さまざまな理由で家や家族を失った男たちの顔は荒んでいた。
ブレーズは下唇を噛んだ。 歴戦の勇士は、引き際を知っている。 いくらなんでも多勢に無勢だ。 顔を歪めて、ブレーズは長い剣を地面に放り出した。 よく手入れされた剣は、大地に当たって鈍い音を立てた。
ジャックは大口を開けて笑い、馬に近づいて手を伸ばした。
「まずその子を下ろしてもらおう」
騎士の腕がミリアムから離れた。 ミリアムは前鞍にかがみこみ、盗賊たちを鋭い眼で見渡していた。 ヴェールがないので可愛い顔が宝石のように浮き上がって見える。 ジャックのすぐ横にいた若い男が、見とれながらつぶやいた。
「すげえべっぴんだ。 金髪じゃないが」
「だまれ」
ジャックは部下を厳しくたしなめ、両腕をさらに差し出した。
「さあ嬢ちゃん。 降りてきな」
ミリアムは、その手にすがってゆっくりと馬を下りた。 だが、足が地面についた瞬間に変身した。 思い切りジャックの向うずねを蹴って腕から逃れると、ふところから薄刃の短剣を取り出して、自らの喉に当てた。
「ちょっとでも近づいてごらん。 喉を突いて死ぬよ」
それは、さっきまでのぼんやりした娘とは別人だった。 眼が星のように輝き、頬は燃えるように赤い。 不意に活気づいて、楽しんでいるようにさえ見えた。
ジャックは、痛そうに脚を撫でながら唸った。
「この小娘が!」
ブレーズが、タンッという音をさせて馬から飛び降りた。 とたんに盗賊たちが蜜にむらがる蟻のように周りを取り囲んだ。
一瞬の静寂をついて、落ち葉を踏みしめる足音がこちらへやってきた。 ブレーズ、ミリアム、そして盗賊たちまでが、音のした方角に顔を向けた。
闇夜の亡霊のように現れたのは、黒い長衣をまとった姿だった。 あの巡礼だ。
彼の姿を眼にしたとたん、ミリアムの指がふるえ、やがてゆっくりと短剣ごと下に下がった。
ジャックは帽子を取って頭をかき、あごをしゃくって子分たちに、ブレーズを連行するよう命じた。 男たちは油断なく6人がかりで大男を回りから押さえつけ、塊になって森の奥へ消えていった。 驚いたことに、ジャックと側近ももうミリアムを見向きもせずに、子分たちの後から歩いていってしまった。
巡礼は無言で黒い馬に近づいた。 馬は首を振っていななき、おとなしく手綱を取らせた。 巡礼はミリアムをまず抱き上げて馬に載せ、後から軽々と飛び乗った。
無言の旅だった。 馬はだく脚で森を抜け、ローダムへの道を辿った。 やがてぽつんぽつんと建った郊外の家々の黄色い灯が目に入ってくると、ミリアムは激しい緊張がゆるんで泣きくずれそうになった。
シメオンの家の少し手前で、巡礼は馬を止め、ミリアムが降りるのに手を貸した。 そして遂に一言も口をきかず、馬の首を回して、もと来た道を引き返していった。
足を引きずるようにして門をくぐったミリアムは、家政婦の魂切るような叫び声に迎えられた。
「わあーっ、お嬢様、お嬢様あ!」
たちまち裏口から、厩から、奥の納屋からまで人が駆け出してきて、ミリアムを取り巻いた。
「お嬢様!」
「よくご無事で!」
「戻ってこられたなんて奇跡だ!」
上半身をふらふらさせていたミリアムは、やっと力を振り絞って尋ねた。
「お父様は?」
家政婦のスザンナがしゃがれた声を張り上げた。
「寝込んでらっしゃいますよ! お嬢様を城まで迎えに行って、ついさっき戻ってきなさって、それからおいおい泣いて」
「ミリアムはぎゅっと眼を固く閉じた。
「お父様……」
ほぼ同時に玄関から男の姿が飛び出してきた。 あまりの喜びにガウンを着るのも忘れ、長い縞模様の寝巻き姿だが、空を飛ぶようにミリアムに抱きつき、半分持ち上げて抱きしめた。
「ミリアム!」
「お父様」
ミリアムは切なげに言った。
「お父様、私……」
後は涙で言葉にならなかった。
月はリュック・ドラペーズの城をも公平に、青白く照らしていた。 再び引き上げられた跳ね上げ橋の前に、馬がゆっくり歩み寄って、脚を止めた。
1頭ではなかった。 次々と連なって城の前に集まってくる。 やがて総勢15騎になった。
最後の1頭が到着したのを確かめて、先頭の乗り手が大音声で叫びかけた。
「城内のお方! 橋を下ろし、門を開けてください!」
やがて窓辺で灯りが動き、城門に人影が現れた。 まだ若い、少年の声が響いた。
「どなたですか。 このような深夜に城を開けろなどと」
二番目の馬に悠々と乗っていた男が前に進み出て、命令し慣れた調子で答えた。
「この国の王、リチャード・プランタジネットだ」
あわてて見張り台から転げ落ちたような音がして、玄関の大戸がきしみ、5分ほどすると今度は大きく開け放たれた。
中からリュックが飛び出してきた。 そして、さっさと橋を下ろすよう部下に命じた後、汗を拭きながら城門に立った。
「これは陛下。 今すぐ通れるようにいたしますので」
「早くしてくれ。 長旅で疲れている」
国王は短気丸出しでそう言った。
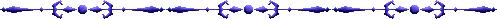
 |  |  |
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
