

エニッドが連れ込まれた3階の部屋では、大変な騒ぎになっていた。 戸口から足を踏み入れたとたん、エニッドは駆け出し、目に付くものを手当たり次第にリュックに投げつけ始めた。
「何するのよ! このろくでなし! 犬のはらわた! 豚の尻尾!!」
酒瓶や壷が空を切って飛んでくるのをよけながら、リュックは声を振り絞った。
「愛しているんだ! 大切に守るから!」
「これがあなたの守り方なの!」
エニッドはすっかり逆上していた。
「相手はしてあげたじゃないの! 2度、いや3度だったかな……回数なんかどうでもいい! ともかく、千回生き返っても、あなたの奥さんになんかならない!」
「エニッド!」
「なれなれしく呼ばないで! 朝起きて真っ先にあなたの間抜け面を見るのなんか絶対に、嫌!!」
廊下を数歩引きずっていった後で、ミリアムが本当に歩けなくなっていることを知り、ブレーズは軽々と彼女を肩に担ぎ上げ、階段を上った。 リュックの部下2人とすれちがったが、どちらも目を合わせないように急ぎ足で下っていった。 ブレーズに狩の獲物のように運ばれていくミリアムを気の毒に思っているのだろうが、とても手を出せる雰囲気ではない。 それほどブレーズの顔は迫力があり、周りを威圧していた。
自分用に割り当てられた寝室に入ると、ブレーズはミリアムをベッドに文字通り投げ落とし、壁にあいた小さな窓を閉めに行った。
鎧戸〔よろいど〕をぴたりと閉じた後、その戸を背にして、ブレーズはミリアムに向き直った。 鋭い視線が少女を射すくめた。
「わかっているんだろうな。 おまえはもうわたしから逃げられないということを」
ミリアムははっきりわかるほど震え出した。 ブレーズは、悠々と服を脱ぎはじめた。 まず上着を取り、ズボンを外す。 テンプル騎士団のならわしとして、羊皮のズボン下をはくことになっていて、今では大部分の騎士がこっそり脱いでしまっているが、ブレーズはちゃんと身につけていた。
間もなく上半身が露わになった。 着やせする方らしく、思ったより肩幅が広くて、胸と背中がしなやかな筋肉で覆われていた。
ズボン下に手をかけたとき、かすかな音がした。 ブレーズは動きを止め、野性の獣のようにかがんで耳をそばだてた。
2度目は、ミリアムにも聞こえた。 それは鋭く吹き鳴らされる角笛の音だった。
同時にドアが叩かれた。 少年のおびえたような声が中まで響いてきた。
「すぐおいでください。 殿下が二階でお待ちです」
ブレーズは身を起こし、舌打ちした。 そして不機嫌な太い声で応えた。
「今行く」
そして今度は素早く服を身にまとい始めた。
数秒で着終わると、ブレーズはミリアムをにらみ、釘を差した。
「ここを出るんじゃないぞ。 逃げたりしたら、どこまでも追いかけていくからな」
ミリアムはかすかにうなずいた。
また遠慮がちなノックが聞こえた。
「お願いです。 必ず呼んでこいと言われてますので」
「今行く!」
怒鳴り返して、ブレーズは短剣を腰に差した。 それからいきなりミリアムを抱き取り、唇を奪った。
むさぼるようなキスだった。 砂漠で水を見つけた旅人がしゃにむに飲み干すように、飢え乾いた口づけだった。 だが時間は短く、ほんのひとときでミリアムを突き離すと、男は大きな足音を立てて去っていった。
ブレーズが広間に入っていくと、ジョン親王が困った顔で近寄ってきた。 そして窓の方を顎でしゃくってみせた。
「外にシメオン・レヴィが迎えに来ている」
ブレーズは暫定王を見返した。
「それで?」
ジョン王子の肩が心なしかしぼんだ。
「シメオンは金貸しだ。 ここいらの武士たちはたいてい、彼から金を借りている。 穏やかで取立てがそう厳しくないからだ。 つまり人望があるのだが」
「それで?」
長引く前置きに、ブレーズの目が三角になり始めたので、ジョン暫定王はあわてて言った。
「貴公が連れていった娘、あの子はそのシメオンの一人娘なのだ」
「だから?」
ブレーズの顔は微動もしなかった。 ジョン王子は咳払いした。
「だからその、あの娘、ミリアムを返してやるわけには……」
「いやです」
一言の元にはねつけて、ブレーズは部屋を出て行ってしまった。 荒い足音が遠ざかるのを、ジョン王子は口をあけて見送った。
椅子に片脚を上げていたマルクが、あざけるように言った。
「あれだけリュックを馬鹿にしていたくせに、自分が惚れると、なんてざまだ!」
「まずいな」
王子は思わずつぶやいた。
「ヘブライの民は教会の許可を受けて商売しているのだから、奴らとことを構えると面倒なことになる」
廊下に出ると、ブレーズは語気荒くリュックの従者を呼びつけた。
「おい! すぐわたしの馬を用意しろ」
「馬、ですか?」
「そうだ」
ブレーズの黒っぽい眼は、得体の知れない感情に燃えさかっていた。
「さっさとしろ!」
「はい!」
リュックはまだ三階にいるらしく、暇だった従者は大あわてで裏階段を駆け下りていった。
唇を一筋に結んで、ブレーズは大股に階段を上った。 部屋の前で足を止め、気配をうかがったが、何の物音もしない。 そこで、ガッと勢いよくドアを開いた。
ミリアムは床にひざまずいていた。 神に祈っていたらしい。 戸口で仁王立ちになった男を見て、すぐに立ち上がった。
ブレーズは石のような表情で言った。
「殿下はわたしからおまえを取り上げたいらしい。 だが、そんなことはたとえ親王でも許さない。 さあ、来るんだ!」
男の強い腕が少女の体に巻きつき、再び軽々と持ち上げた。
シメオンは、なかなか降りてこない跳ね上げ橋の前で、冷たくなった指先に息を吹きかけながら待っていた。 晩餐会に出かけるまでは許したが、泊まっていいとは許可していない。 結婚前の娘なのだ。 返してくれて当然だった。
ずいぶん待たされた。 冬が近いので、辺りは漆黒の闇。 用意した松明が尽きかけたころ、ようやく巨大な龍のあぎとのような跳ね上げ橋が、揺れながら降りてきた。
ほっとして、シメオンは用意した馬とロバ、それに若い従者ふたりを従えて、城門をくぐった。 だが玄関の大門を開いて出てきたのはかわいい娘ではなく、苦虫を噛みつぶした顔のマルク・ド・ボア・ルージュだった。
マルクは怒鳴るようにシメオンに告げた。
「娘はいないぞ」
シメオンは驚いて身を乗り出した。
「姫様たちともう帰ったので?」
「いや」
さすがのマルクも、次の言葉は言いにくかった。
「さっきまで 客人がもう一人来ていた。 歴戦の勇士なのだが、その男がミリアムを見たとたんにのぼせてしまって」
さっとシメオンの顔から血の気が引いた。
「何とおっしゃいました……?」
早口で、マルクは言い終えた。
「止めるのも聞かず、さらっていってしまった」
そして、茫然と立ち尽くす父親から目をそらし、さっさと城に引き返した。 重い門がきしり音を残してゆっくりと閉じた。
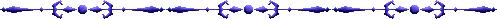
 |  |  |
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
