

その夕方は穏やかな気候だった。 凶事を暗示するようなきざしはどこにもなく、ハロルド・ハンコックに先導された招待客たちは、なごやかに道を辿っていた。
美麗な灰色の馬に横乗りしたエニッドは、隣りで用心深く栗毛にしがみついているミリアムに盛んに話しかけていた。
「だからロンドンに行って東洋から運んできた腕輪を買ってきてくれと頼んだのよ。 それなのにエドワードが何を買ったと思う? 聖書よ! ろくに字も読めないくせに。 中を開いたら色つきの絵があって、きれいだったからですって!」
「エドワード様は読み書きを習いたいんですよ、きっと」
「なぜ? 書記か家令に命じれば、読んでくれるじゃないの」
「それはそうですけど」
書物はさまざまなことを教えてくれる。 その中身は形がないから、いくら頭に詰め込んでも人に知られずにすむ。 知識は力だと、父のシメオンは教えてくれた。 だからミリアムはギリシャ語、ラテン語、それにヘブライ語で楽々と読み書きできるようになっていた。
もちろんエニッドには話していない。 お姫様は教養がなくても優雅に暮らしていけるから。
さっと風が吹きなびいて、話題の主、エドワード・ハンコックが馬を寄せてきた。 槍試合の日、石弓で巡礼をおどした若者だ。 夢のようにきれいなのは相変わらずだが、今はきゅっと眉根を寄せて、不快そうだった。
「エニッド、またその話をする。 やめてくれ、わたしを冗談の種にするのは」
「本当のことでしょう?」
エニッドはつんとした。
「坊さんになりたいならともかく、その歳で学問したいだなんて」
「その歳って、わたしは21だ!」
「16で結婚してる人だって多いんだから」
「まだ誓いの絆で縛られたくない」
「あれは縛るんじゃなく、結びつけるの」
2人の口喧嘩を聞いていたミリアムの額が曇った。 そして、乗っている栗毛の速度を下げ、後ろに退いた。
跳ね上げ橋の両端は大きな松明〔たいまつ〕で赤々と照らされていた。 リュック・ドラペーズの従者たちがずらりと並んで出迎える中、ハロルドたち一行は気持ちよく城に入っていった。
すべての人間が入城し、馬から下りて城の中に消えると、間もなく跳ね上げ橋が静かに引き上げられた。 午前中に油をさしておいたので、音もなくなめらかに。
宴会場は、慣例どおり二階の大広間にしつらえられていた。 部屋の真ん中に煌々と燃える大きな炎がまぶしい。 しかし、少し離れると薄暗かった。
長テーブルの上にはご馳走が所せましと並べられていた。 いのししの大きな切り身には蕪が添えられ、ガチョウの丸焼きが人参とタマネギに埋まっている。 ワインをたたえた盃がずらっと並んで、なかなかの眺めだった。
ジョン親王は上機嫌でエニッドをそばに座らせ、ハロルドのがっしりした顔に笑いかけた。
「よく来てくれた。 くつろいで沢山食べてくれ」
料理を用意したのは城の主人であるリュックなのだが、まるで自分が準備したように言って、ジョン王子は真っ先に座った。 それから人々は席についた。
一番末席で、遠慮がちにミリアムは座っていた。 自然にハロルドたち主賓と切り離されてしまったので、話し相手がいない。 黙ってうつむいているしかなかった。
食事はなごやかに進んだ。 それが一変したのは、エドワードが厩に物を取りに行こうとして、出口が開かないことに気付いたときだった。
ハロルドは我が目を疑った。 いくらノルマンが征服者とはいえ、ここまで露骨な強圧策を取るのはめったにないことだ。 しかもこれまで、ハロルドはドラペーズ兄弟とはうまくやってきた。 それなのにこの豹変ぶりは!
ジョン王子が立ち上がり、言葉だけは穏やかに、つられて立った一同に語りかけた。
「実は今宵をめでたい夜にしようと思って呼んだのだ。 エニッド姫、ここにいるリュック・ドラペーズと結婚なさい。 これは王としてのわたしの権限であり、したがって命令である」
エニッドは思わずテーブルの端につかまって体を支えた。 華やかな顔がまず青ざめ、それから次第に赤く変わった。
「恐れ入りますが、殿下」
聞こえないふりをして、ジョン親王は手を叩いて部下を呼んだ。
「めでたい席だ。 とっておきのボルドー・ワインを持ってこい!」
「殿下!」
泣きそうになって、エニッドはわめいた。 ハロルドも目を怒らせて進み出た。
「納得いきません。 わたしは13のときから姫の後見人をしております。 結婚話はわたしを通じてなすべきもの。 これでは筋が違います」
「反対だというのか?」
ジョン王子は静かに、ごく静かに尋ねた。
ミリアムは炉から一番遠いところにいた。 だから目立たぬように斜め横に動いて、柱の陰に身を寄せた。 心臓が不規則にとどろいている。 背筋に氷のような恐怖が這い上がってきた。
ジョン親王の行為は、明らかに暗黙のルールを破ったものだった。 相当の覚悟があってやっていることだ。 となれば、誰にも容赦はしないだろう。 生まれて初めてミリアムは、真に身の危険を感じた。
困ったことに、ハロルドは正直だが頑固一徹の古武士だった。 言葉を二重に操ったり、人の行動の裏を読むなどということは、間違ってもできないタイプだ。 だから率直に突き進んでしまった。
「納得いかないと申し上げているのです。 姫のお心を訊きませんと」
「それでは姫、リュック・ドラペーズ殿のどこが気に入らないのかね?」
エニッドの頬が引きつった。
「いえ、あの…気に入らないということではなく」
「それはいい。 ではここで婚約を。 ふたりとも手を出しなさい」
王が手づから男女の手を結び合わせれば、即婚約が成立したことになる。 エニッドは前に進み出るどころか、後ずさりして、椅子に転げこんでしまった。
すかさずリュックが進み出てエニッドの手を求めた。 とたんに短気なエドワードが走りよって、リュックの前に立ちふさがった。
もみ合いが始まった。 宴会場に入る前に物騒な長剣は預けているので、男たちが持っているのは短剣だけだが、それでも危険はそう変わりない。 差すことも、投げることもできるからだ。
サクソンの男たちは勇敢だったが、相手は準備していて、しかも人数がはるかに多かった。 間もなくハロルドとエドワードの親子は数人によってたかって押さえこまれて、身動きできなくなってしまった。 従者数人も同じ目に遭わされていた。
意気揚揚と、リュックはエニッドの手を取って広間の奥へ導いていった。 小姓が戸口を開き、2人は暗い廊下へ姿を消した。
エニッドに従ってきた2人の小間使いは、もう笑ってはいなかった。 追いつめられた野ウサギのような表情になって、まずエニッドの後を追おうとし、引き止められて2人で抱き合った。
ミリアムは柱の背後に張り付いていた。 もう近くには誰も味方はいない。 絶体絶命だとわかっていながら、どこかに救いがないかと、眼だけ動かして探っていた。
そのとき、後ろの扉が音もなく開いたので、ミリアムは心臓が止まるほどびっくりして、4分の1柱を回り、入ってくる連中からできるだけ身を遠ざけた。
それは、ジョン王子の命でボルドーワインを持ってきた2人の従者と、護衛するようにその後からついてきた長身の男だった。 ミリアムが忙しく視線を動かしていると、偶然その大男と眼が合った。 初めて見る顔だ。 松明を横にかざしているので、影が左頬に伸び、ノルマン特有の鷲鼻を強調している。 一見して鬼のように見えた。
部屋の向こう側から、別の松明が近づいてきた。 残党がいないかどうか、確かめているらしい。 炎が縞模様をつけているその顔は、ミリアムがレジナールと同じほど嫌っている、ならず者のマルク・ド・ボア・ルージュのものだった。
ミリアムを発見したマルクの口が、にやりと歪んだ。
「おや、誰かと思えば意外な珍客だな」
それから、すっと手を伸ばして、ミリアムのヴェールを引きはがした。
ミリアムはひらりと身をよけ、柱の反対側に回った。 マルクは鬼ごっこでもしているつもりらしく、わざとゆっくり少女に忍び寄った。
「ほれ、今宵の戦利品に、ヴェールをいただいた。 ついでに中身も」
ミリアムは進退窮まった。 柱の途中にはあの見知らぬ男がいる。 無関心な表情で、場所もあろうにその柱に寄りかかって、ミリアムの退路を塞ぐ格好になっていた。
マルクはさらに一歩進んだ。 そのとたん、ミリアムは思いがけない行動に出た。 不意に柱から離れて、大男の横に身を寄せた。
追いつめられて他に行けなくなったから、自然にそうなったように見えた。 マルクもそう思い、大口を開けて笑いながら両手を伸ばした。 すると、娘は大男の背中に回り、服の袖をしっかり掴んでしまった。
これはどう見ても、庇ってほしいと願っている姿だった。 マルクの顔が驚きに赤らんだ。 しがみつかれた男の顔も、意外な展開に強ばった。
マルクは無理に微笑を作り、からかうような調子で言った。
「その人は柱ではないぞ。 手を離せ」
しかし、ミリアムは離れるどころか、ますます強く男にすがりついた。 マルクは息を吸い、ブレーズ・ド・サンジュストを一睨みした。
「そこをどいてはもらえないか。 おぬしには関係ないことなのだから」
ブレーズの肩が動いた。 そして、マルクのみならず、他の騎士たちまでがあっけに取られるような言葉が、口から出た。
「獲物は公平に分けるのが決まりだ。 この女はわたしが頂こう」
そんなに大きな声ではないのに、広間中に響き渡った印象があった。 ノルマンの騎士たちは顔を見合わせ、ジョン王子でさえ口をあけてブレーズを眺めた。
ミリアムは小刻みに震え出した。 その姿を見て、マルクは腹立ちまぎれに怒鳴った。
「自分が招いた災厄だ! わたしと違ってその男は容赦ないぞ。 『幽霊』と呼ばれてサラディンの軍勢に恐れられた猛者なんだ!」
「畜生! その汚れた手を離せ!」
部屋の端からエドワードの叫び声が聞こえた。 だが捕らえられた若者の威嚇など、ブレーズにとっては鶏のときの声よりささいなものだった。 彼はぞんざいに少女の手を取り、引きずるようにしてドアから出ていった。
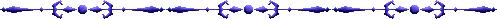
 |  |  |
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
