

計画は木曜日に実行されることになった。 さっそくジョン親王の名前で招待状が出され、折り返し承諾の返事が届いた。
いよいよ決行の日、リュックは一人わくわくしていた。 落ち着きなく歩き回ったり、いつもは乱暴に腹を蹴る馬をよしよしと撫でたりしている。 まだ婚約が決まったわけではないのに有頂天になっている青年を、ブレーズはうんざりした眼で眺めた。
「あのように浮き立っていて、ちゃんと計画どおり動けるでしょうか」
ジョン王子は口髭をひねった。
「どうかな。 しかし、彼がいないと求婚が成り立たないしな」
「それはそうですが、肝心の城主があんな有様では、計画が隅々まで行き届くかどうか……」
「貴公に監督は任せる。 疲れているのに悪いが、よく見回って見落としのないようにしてくれ」
仕方なく、ブレーズは頭を下げた。
マルクがそばに来て、部屋の端に唾を吐き、十字を切ってから報告した。
「裏門を閉じました。 跳ね上げ橋は、何度か試してみて、すぐ上げられるようにしてあります」
「ご苦労」
マルクはブレーズをじろっと見て、聞こえよがしにつぶやいた。
「さて、お手並み拝見だ。 よそ者の北部人にこの土地の事情がどこまでわかるか」
ブレーズは相手にせず、ジョン暫定王をうながして奥へ入ってしまった。 マルクは舌打ちし、また唾を吐いた。
「どうしよう。 ねえ、この青いのがいい? それともこの真紅の?」
侍女たちは笑いさざめきながら答えた。
「どちらも本当によくお似合いで」
「お姫様は何を着ても花のようですわ」
形のいい口を突き出して、エニッドは絨毯の上に座り込んでしまった。
「晩餐会なのよ。 一応とはいえ、今の王様のご招待なんだから、一番似合うものを着ていきたいの。 お世辞なんかやめて、教えてよ」
侍女のアンとエセルは顔を見合わせた。 そして声を揃えて答えた。
「でも」
「でも、どれもお似合いですから」
従順な召使に訊いても、らちがあかない。 はきはきしているのになぜか決断力に乏しいエニッドは、ここで幼なじみを思い出した。
「そうだ! ミリアムに訊きましょう。 あの人は、この狭い土地に閉じ込められてる私とちがって、スペインにもギリシャにも行ったことがあるから、いろんなことを知ってるの。 服の趣味もいいし。
アン、リスベスにミリアムを呼んで来てもらって。 ジョン親王に紹介してあげる、親王に気に入られればお父さんの商売にもいいからって」
「はい」
「はい」
若い侍女たちは共に答えて、なぜか2人一緒に出ていってしまった。 エニッドはフーッと息をついた。
「まったく、にぎやかなだけで気のきかない子たち!」
ここ数日、ミリアムは口数が少なくなっていた。 娘がおとなしくなってしまったので、シメオンは心配で、ウォンクリフの町に従者の様子を見に行くのをためらっていた。
「気分が悪いのか? どうしたんだ。 いつもあんなに元気なのに」
ものうげに窓辺を離れたミリアムは、父親の手に触れて、そっと握った。
「大丈夫よ、お父様。 頭痛が取れないの。 大したことじゃないんだけど」
本当に痛いのは心だということを、ミリアムは自分にも隠していた。
楽しかった勝利の宴の翌朝、ミリアムは早起きして倉庫に行った。 巡礼の服があまりに痛んでいるので新しいマントを手渡そうと思いついたのだ。
薄暗い倉庫を覗くと、ちょうど巡礼が起き出してくるところだった。 あわてたように頭巾を引き下ろし、杖にすがって立ち上がっている。 せまい倉庫だと長身がますます大きく見えた。
いつも通り、ミリアムは気軽に話しかけた。
「失礼だとは思いましたが、その服はかぎ裂きができていますから、新しいものを着ていってください。 できるだけ大きいのを持ってきました」
巡礼は黒い影のように立っていたが、間もなく信じられないことをした。 大きな片手を振って、出ていけと合図したのだ。
ヤギか羊を追うような手まねをされて、ミリアムは血の気が引くのを感じた。 こめかみが脈打って、胃がむかついてきた。
それでも怒りを押さえ、ミリアムは静かに言った。
「それではここに置いていきますから、お気に召したら着てください」
巡礼は何の反応も見せない。 ミリアムはドアを閉めて、速足で家に戻った。
部屋に入ったとたん、目頭が熱くなって、ミリアムは慌てた。 失礼な態度を取られたのは確かに悔しい。 でもそれ以上に、巡礼の気にさわることを何かしたのではないかと、反省が先に立った。
(人前で踊ったりしたからかしら。 はしたない女だと思われたのかも…… それよりやはり、槍試合に出てくれなんて生意気なことを頼んだから……)
いくら考えても決定的な原因に思い当たらない。 不意に冷たくされた事実だけが胸をえぐった。
そのうち、気がついた。一人でくよくよしているより、直接訊けばいい。 反応の速いミリアムは、さっと身をひるがえして階段を駆け下りた。
しかし、もう遅かった。 走っていったにもかかわらず、すでに巡礼の姿は、倉庫にも、見渡すかぎりの道筋にもなかった。
行ってしまった。 別れの挨拶もなしに。 ミリアムには信じられなかった。
その時から、ミリアムにふさぎの虫が取り付いた。 明るい少女には初めてのことで、シメオンがおろおろするのも無理はなかった。
だから、にぎやかにやってきたリスベスの誘いに、父親のほうが喜んだ。
「ありがたいお申し出で。 あの子はちょっと落ち込んでいるようなので、いい憂さ晴らしになるでしょう」
ミリアム自身もそう思った。 異教徒だから、華やかな王族の晩餐会に招かれることはほとんどない。 たまに父が招待されることがあっても、未婚の娘を連れていくことはなかった。
でも家柄のいいエニッド様が守ってくれるから大丈夫――そのときのミリアムは、そう信じていた。
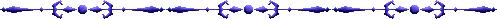
 |  |  |
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
