

その夜、シメオンは、友達数人と小さな楽団を呼んでいた。 巡礼がみごとな勝利を収めた祝いの宴を催すために。 闘った相手が相手だけに、大っぴらに騒ぐことはできないが、奥の部屋でそっと盛り上がった。
主賓のはずの巡礼は、部屋の隅でひっそりとワインを飲んでいたが、それでも楽しそうだった。
やがて興が乗った客の一人が、ミリアムにせがんだ。
「せっかく楽団があるんだ。 踊ってくれないかね。 あのかわいいスペインの踊りを」
ミリアムはちょっと頬を赤くして微笑んだ。
「人前で踊るほどのものでは」
「そんなことはない!」
うんうんと、人々はうなずきあった。
「めでたい席なんだ。 ちょっとだけでいいから」
ふだん飲めない酒を口にしたシメオンまでが盃を上げて娘に呼びかけた。
「踊ってごらん。 ほら、あの鈴を持って」
それは縁に金属片のついた、小型のタンバリン状の楽器だった。 ためらいながらもミリアムは広い部屋の中央に進み出て、小さな靴を軽く踏みならした。
それが合図だった。 楽団が短調の曲をかなで始め、ミリアムは背をそらして踊りだした。
きれいにタイルされた床に軽い足音が響く。 曲は次第に速さを増し、ヴェールの下からひらめくミリアムの頬が愛らしく紅潮してきた。
座って見とれていた若者が、すっと立ち上がって床にかがみ、両腕を前に組んで踊りに加わった。 すぐに一人、もう一人と男たちは踊りの輪に入り、立って優雅に舞っているミリアムを中心にぐるぐると動きはじめた。
それは不思議なほど統制の取れた輪舞だった。 楽しげな人々から眼を離さずに、巡礼は2杯目のワインを飲み干した。
宴は8時ごろにお開きとなった。 戸口で客たちを見送ったシメオンは、さっそく巡礼を昨夜と同じ部屋に案内しようとしたが、巡礼は丁重に断った。
「少し酒が入ってしまったので、いっそう悪夢にうなされると思います。 納屋で寝かせてください。 それがだめなら野宿します」
仕方なく、シメオンは庭の端にある倉庫に案内した。 そこなら納屋と違って扉がしっかり閉じるので寒くない。 召使に命じて寝心地のいいマットを運ばせた後、シメオンは残念そうに言った。
「本当にこんなところでいいんですか? 大事なお客様を粗末にしているようで」
「とんでもない」
巡礼はやさしく答えた。
「私の勝手なお願いですから。 それではおやすみなさい」
「ゆっくりお休み下さい」
2人は互いに礼をして別れた。
ひとりになると、巡礼はマットを軽く叩き、満足げにつぶやいた。
「なかなかいい。 これならよく眠れるだろう」
同じ夜、アイルマーの町で、ジョン親王と部下たちは、憂さ晴らしの宴会を催していた。 長いテーブルの上にも下にも食いかけの腿や肉片のついた骨が散らばり、犬たちが尻尾を振りながらかじりついていた。
騎士や従者たちが椅子にまたがったり立ったりして自棄酒〔やけざけ〕の乾杯を繰り返していたとき、小姓が入ってきてジョン王子に耳打ちした。
不意に酔いが半ば醒めて、ジョン王子は小姓に訊き返した。
「本当なのか? 本当にそう名乗ったんだな?」
「はい」
世間知らずの小姓は、不思議そうにうなずいた。 とたんに王子は立ち上がり、大音声で呼ばわった。
「聞け! 驚くなよ。 ブレーズ・ド・サンジュスト殿が来たそうだ!」
ノルマンの騎士たちは一斉に身を起こし、戸口に視線を集めた。
小姓に長剣を外して渡しながら入ってきたのは、身の丈2メートル近くありそうな偉丈夫だった。 眼光はけいけいと鋭く、口元は厳しい。 じろっと睨みわたされて、酔いの回った猛者たちでさえ気おされた。
顎を上げると、遠来の騎士はさげすんだ口調で言った。
「うさ晴らしか。 なんでも飛び入りの男にぶちのめされたそうじゃないか。 シャルル、寺侍の恥だぞ!」
名指しされたシャルル・ド・スイフは、困って鋭い視線を避けた。
「わたしは戦っていないから……」
「まあまあ」
ジョン親王がなだめに入った。 急に機嫌がよくなっている。 それほどブレーズ・ド・サンジュストは頼もしい味方だった。
「よく来てくれた。 だがもう2日、せめてもう1日早く着かれれば、わが方は勝利間違いなしだったのだが」
「長旅で疲れました」
そっけなく言って、ブレーズは大股で長テーブルに近づいた。 騎士たちが自発的に席を譲り、ブレーズはジョン王子のすぐ隣りに座った。 そのぐらい、ブレーズ卿の勇名は国境を越えて鳴りとどろいていたのだ。
一同の中で、これまでブレーズ卿に会ったことがあるのは、シャルル・ド・スイフとリュック・ドラペーズぐらいだった。 それも顔を見知っている程度で、親しくしている者はなかった。 そもそもブレーズ卿は、口をきくこと自体がまれだったのだ。
変わり者が多いテンプル騎士団の中でも、ブレーズ・ド・サンジュストは飛びぬけて理解しにくい男だった。 したがって、彼ほど様々な風説に彩られた騎士は他になかった。 まさに『生きている伝説』だ。 フランスの小貴族の出なのは確かだが、庶子とも養子とも言われ、一説によると妻殺しとまで噂されていた。
本人は、どの噂もまったく意に介さなかった。 テンプル騎士団は一般の騎士たちと違い、前科があろうが前歴があろうが、今神に仕える気があれば許されるので、後ろ暗い貴族の末裔たちが大勢参加している。 過去を問う者などいなかった。
霧にかすんだ過去はどうあれ、ブレーズ・ド・サンジュストはテンプル騎士団の華、寺侍の鑑〔かがみ〕となっていた。 当初の規律を失い、ならず者の集まりに近くなっていた騎士団で、ブレーズはあくまでも節制と鍛錬を貫きとおした。 だからこそ騎士団随一の剛の者になれたのだが、ブレーズには更に高い能力があった。 意表をついた計画を立て、冷静に実行する能力だ。 まさに闘うために生まれたような男だった。
ブレーズが来たことで座は一挙に盛り上がり、酒盛りは夜が明けるまで続いた。 騎士の大半が椅子に寄りかかり、幾人かは犬と共に床に寝転がっていびきをかき出した朝の8時ごろ、ブレーズはジョン親王に耳打ちした。
「本部から書面を預かってきています」
親王の顔が引きしまった。
別室で巻紙を開いたジョン王子は、しかめ面になった。
「リチャードが逃げた?」
ブレーズはうなずいた。
「神聖ローマのハインリッヒ6世に捕まっていたのが、どうにかして抜け出したらしいです」
いまいましげに手紙を投げ捨て、ジョン王子は部屋をせわしなく歩き回っていたが、そのうち、つい本音を吐いた。
「ハインリッヒのやつ、始末してくれればよかったんだ」
ブレーズはにやりと笑った。 目は冷たいままで口元だけゆるめるので、はたから見ると悪魔のようだった。
また部屋を一回りしたあげく、ジョンはブレーズを見上げた。
「どうしたものかな」
「金です」
ブレーズは簡潔に答えた。
「リチャード王は莫大な戦費を使って十字軍を組織しました。 騎士たちはみな食うにも困っています。 ここで殿下が彼らに恵みを与えれば、人心はこぞってあなた様のものです」
ジョン王子は顎を撫でた。
「しかし、財政が乏しいのはわたしも同じなのだ。 実をいうと」
「なければ作るのです」
暗い光がブレーズの眼をかすめて過ぎた。
「われわれノルマンとは違う人々が、この国にはいるはず」
「だが」
ジョン王子は内心ぎょっとして目をあげた。 小心者なので、大きな悪事には踏み切れないのだ。
しかし、ブレーズは容赦しなかった。
「サクソンの連中は、長くこの地を牛耳ってきました。 でも、彼らもしょせん侵入者。 歴史をたどれば我々と同じことをやっているのです」
珍しく雄弁に、ブレーズは道々立ててきた計画を語った。
「このあたりにはまだサクソンの大地主が何人もいますね。 エドウィン・オズボーン、ハロルド・ハンコック。 それに、そうそう、エニッド姫という評判の美人も、たしかシャルデンの森の外れまで広大な土地を持っているとか」
「わずかの間によく調べたな」
ジョン王子は舌を巻いた。 当然のことという様子で、ブレーズは続けた。
「こういう計画はいかがでしょう。 ハンコックはエニッド姫の後見人で、よく一緒に行動しているそうですから、両者をドラペーズの城に招待して、姫とリュックの婚約をまとめてしまうというのは」
王子の目が大きく開かれた。
「おぬし……リュック・ドラペーズが姫に夢中なことまで調べ上げたのか」
「調べるまでもありません」
ブレーズは苦々しく言った。
「あの男は遠征軍で姫の肖像画を肌身はなさず持ち歩き、しかも回り中に見せびらかしていました。 阿呆です」
「女嫌いなおぬしから見ればそうだろうがな」
「ともかく」
女の話題はたくさんとばかり、ブレーズは話しつづけた。
「代理国王の権限で婚約をお決めください。 ハンコックが反対したら、それこそ好機です。 反逆罪で領地を没収し、どうなりと好きにできます」
あっけに取られて、王子はブレーズを見た。 それからつぶやいた。
「貴公、なかなかの悪党だな」
ブレーズはかすかに笑った。
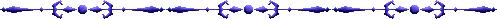
 |  |  |
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
