

外の空気は未だに湿気を帯びていて重かったが、一歩清潔な家に踏み込むと、とびはぜる炎を包む大きな暖炉のおかげで、中はからりとして気持ちのいい暖かさだった。
もう少しでこの我が家に戻ってこられなかったのだと思うと、シメオンは身震いがした。 そして、改めて巡礼への感謝の思いで一杯になった。
「さあ、どうぞどうぞ、こちらの火がよくあたる方へ」
見ると、ミリアムが奥から熱いスープを運んでくるところだった。 小柄な娘は、スペイン風の器に入ったそのスープを、まず巡礼に、それから父親に手渡した。
「野菜だけで作っていますから、安心してめしあがれ」
「ありがとう」
低く言って、巡礼は一口そっと飲んだ。 シメオンは嬉しそうに喉をごくごくさせて飲み干した。
「今日は一段といい味だね」
「いつもほめすぎよ、お父様。 一人しかいない娘がうぬぼれ屋になってもいいの?」
ほれぼれとミリアムを眺めながら、シメオンは太鼓判を押した。
「おまえがうぬぼれたりするものか。 ここいらで一番のいい子だよ、おまえは」
手放しの親バカぶりに、ミリアムは困って、巡礼の方に視線を向けた。
巡礼も、すでにスープを飲み終わっていた。 確かにおいしかったらしい。 だが彼は別に何も言わず、入れ物を脇に置いて、ひっそりと炎に見入っていた。
何となく近寄り難い空気だったので、ミリアムは間接的に父に言うことにした。
「それではお客様のために、二階に部屋を用意させるわね」
「ああ、そうしてくれ」
相変わらず身動きしない巡礼にちらっと視線を投げて、ミリアムは軽い足取りで奥に入っていった。
嵐の去った夜は静かだった。 風に吹き飛ばされたのか、コオロギさえなりをひそめているので、静寂が辺りを完全に支配していた。
だが真夜中過ぎ、異様な音がしじまを裂いた。 獰猛な獣の咆哮に似たその音響に、建物の端に部屋を持つミリアムでさえ飛び起きた。
ねほけ眼で、ガウンに半分袖を通した姿で、シメオンは廊下に出た。 すると、開いた窓のそばに黒い姿がうずくまっているのが目に入った。
足音を聞きつけて振り向いた巡礼は、かすれた声で詫びた。
「申し訳ない。 こうなることがあるので、泊めていただくのは納屋がいいと言ったのです」
「いったいどうなさった」
心配げに、シメオンは尋ねた。 巡礼は、頭巾を深くおろしたままの頭を振った。
「わたしは汚れているのです。 両の手は血にまみれ、耳には断末魔の声が張りついています」
「ああ…」
理解して、シメオンは巡礼の横にそっと膝をついた。 この男は兵士なのだろう。 やむなく殺戮〔さつりく〕を繰り返してきて、もう耐えられなくなっているのだ。
「通りすがりのわたしを助けてくださるほどのお方だ。 たとえ敵でも倒すのは気が重いでしょう」
巡礼は答えず、冷え冷えとした夜気に顔をさらしていたが、やがてゆっくり立ち上がって窓を閉めた。
「もう大丈夫です。 お休みください」
2人は、街道用語と呼ばれる、ギリシャ語にペルシャ語その他中東の言語が混じった言葉で話していた。 これは東洋貿易の関係者が作り出した話し言葉で、使えるのは商人が多い。 しかし巡礼は商売人には見えないにもかかわらず、なめらかに言葉を操った。
翌日早朝、まだゆるやかな丘に霧がたなびいている時間に、音もなく裏口から忍び出る影があった。 真っ黒いマントのままで、肩にわずかな荷物を包んでかけ、片手には節くれだった杖を持っている。
静かに歩み去ろうとしたその背中に、ささやき声がかけられた。
「黙って行ってしまうんですか?」
巡礼は唾を飲み込んだ。 驚いたのだ。 そして、驚いた自分にあわてていた。 これまで人の気配を聞き漏らしたことはない。 いくら平和なイングランドでも、こう油断してしまっては話にならない。
やわらかい声は近づいてきた。
「父が教えてくれました。 命を救っていただいたとか。 何とお礼を申し上げたらいいか」
「偶然です。 たまたま私が通りかかったので盗賊たちは逃げたのです」
「そんな!」
ミリアムはころころと笑った。 明るくかわいい声だった。
「あのメイヨーの森のならず者たちが、父のようなたやすい獲物を置いて逃げはしません。 よほど怖くなければ」
巡礼は当惑して杖を持ち換えた。
「お嬢さん」
「ミリアムです。 名前で呼んでください」
「……それではミリアムさん。 わたしなどに構わないでください。 下っぱの兵士にすぎないのですから。 昨夜はもてなしをありがとう。 それではこれで」
「待って、兵士さん!」
素早くミリアムは巡礼に走り寄り、持っていた包みを彼の手にすべりこませた。
「お願いです。 これだけでも受け取ってください」
ずしりと重い包みの中身は、想像がついた。 巡礼は急いで娘に返そうとした。
「受け取れません。 わたしは巡礼です。 神に許しを乞いに行くのに、大金をいただくなどもってのほか」
ミリアムは、かわいい口元を引きしめて少し考えた。
「それじゃ、このお金で頼まれてください」
「え?」
思わぬ提案に、巡礼は道の端に突き出ていた横枝につまずきそうになった。
「おじょ……ミリアムさんがわたしに?」
「ええ」
娘はいたずらそうに眼を光らせていた。
「あなたは強いお方なんでしょう?」
うんざりして、巡礼は念を押した。
「だから言ったはずです。 わたしは下っぱの……」
「下っぱでも強いはずです!」
娘は頑固に言い張った。
「あなたの手を見ました。 分厚いたこが一面に出来ています。 大きくて重い剣を使い慣れている証拠です」
フードの下に隠れた男の顔が鋭くなった。 小娘だと思っていたが、あなどれない。
「あさって、アイルマーの町で大会があります。 ほら、あちこちの町でよくやっている槍の試合」
「馬上槍試合のことですか?」
「そう、それです。 それに、レジナール・ド・マルドロワという騎士が出るはずなんです」
「はい」
「だから、このお金で立派な鎧と槍と馬を手に入れて、マルドロワ殿をやっつけていただきたいんです」
巡礼は唖然となった。
「何ですと?」
ミリアムは口を尖らせた。
「ひどい人なんですよ。 私を見るといつもちょっかいをかけてきて、一人では町を歩けないほどで。 この前なんか、愛人にならないかなんて大声で言って」
「下等な男だ」
珍しく巡礼が強い調子で言ったので、ミリアムは勢いづいた。
「そう思われますよね? だからお願いできませんか? あまり危険はないと思います。 レジナールは弱いんです。 昔から」
ちょっと考えた後、巡礼は言った。
「わかりました。 引き受けましょう」
ミリアムの顔がぱっと輝いた。
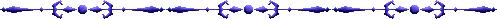
 |  |  |
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
