
―嵐の後で―

シェフィールド近辺では珍しいほどの大嵐だった。 樫のような広葉樹だけでなく、糸杉の細い葉までが吹き飛び、小枝が悪魔の指のように鉤爪形に曲がりながら、雲が渦巻く空を乱舞した。
しっかり握っていても生き物のように襲ってくる鋤を畑に投げ捨てて、ゴードン村のジャックは、頭巾もろとも吹きとばされかけている妻に叫んだ。
「もう帰ろう! 海まで連れてかれないうちによお」
ちなみにこの辺りは低い山が連なっていて、北海からも中海からも100キロは離れていた。
妻のルースは大きくうなずき、風に向かって斜めになりながら、一歩一歩畑から出た。
支えあい、頭を手で守りながら、二人はあぜ道を進みはじめた。
そのとき、グオーッという怪音と共に、シャルデンの森全体が揺れ動いた。 そして体重の軽いルースが、あっという間に宙に浮いた。
「あらまあ!」
ほうきのない魔女のように空を舞いながら、ルースが残したのはそのひとことだけだった。 突風が吹き過ぎると、ルースの小柄な体は畑の隅に叩き落とされ、二度転がって動かなくなった。
「おっかあ!」
ジャックの悲痛な叫びが突風の中に粉々に散らされていった。
一時間後、嵐は嘘のようにぴたりと収まった。 つい今まで耳を引きちぎろうとしていた強風が、突如感じられなくなったので、ナイオ沼のワットがおそるおそる身をひそめていた祠〔ほこら〕から顔を出すと、ひとりの男が森から出てくるのが見えた。
「真っ黒な服着て節だらけの木の杖持ってよお、森から現れたんだ。 こーんなにでっかくてよお、悪魔の化身みてえだったよお」
そうワットは後に語った。 だが、それは悪魔ではなかった。 ワットにもわかっていた。 それは、シェフィールドの寺々を回って歩く、ただの巡礼だった。
その巡礼は、フードを異様なほど深くかぶっていた。 だから目鼻立ちはほとんどわからない。 夕暮れだったこともあって、ワットは背筋が凍え、こんな男に鎌を持たせたら死神そのものだと思った。
だが、傍に来て口を開くと、巡礼の印象はがらりと変わった。 そびえるような痩躯にしては、巡礼は穏やかで気持ちのいい声をしていた。
「たいへんな嵐でしたね」
と、巡礼はゆっくりフランス語で話しかけた。
「まっことそうです」
ワットは愛想よく土地言葉で答えた。 夕暮れ時に他人と会ったら、気分を害させてはいけない。
「道しるべはすべて倒れてしまった。 どうやら道に迷ったらしい」
「どちらへ行かれるんで?」
と、ワットは丁重に尋ねた。 ここいらにはノルマン出身の貴族が多いから、平民のワットでも少しはフランス語がわかる。
巡礼はおっとりと言った。
「アイルマーの町へ」
よく知っている地名だったので、ワットはほっとした。
「それならこの道をまっすぐお行きなさい。 あの小さな森を抜けて、河に突きあたったら右へ」
「河?」
「はい」
身振りを交えて、なんとかワットは巡礼に教えることができた。 巡礼は二度うなずき、感謝の言葉を述べて歩き出した。
「ご親切に。 神のご加護がありますように」
身に合わないものを着ているのに、巡礼の後ろ姿はどことなく優雅だった。
「あれはただもんじゃねえな」
見送りながら、ワットは口の奥でつぶやいた。
シメオンは今にも泣きそうになっていた。 こんなところは娘には見せられない。 7人生まれた子のうちただ一人生き残った、目に入れても痛くない娘には。
「一刻も早く帰ってやらなくちゃ」
石のように切り株の横に倒れているロバを見やって、シメオンは深く嘆息した。
「おい、起きろ。 もう嵐は過ぎたんだぞ。 いつまで気絶しているつもりなんだ」
ロバは答えない。 死んではいないはずだが、今のところ死体より始末が悪かった。
「わたしにその荷物をかついで森を抜けろというのか?」
本当に運が悪かった。 いつもなら従者がいるのに、たまたまウォンクリフの町で腹痛を起こして寝付いてしまった。 そのうえ頼みのロバまでこのありさま。 しかも荷物は貴重なものばかりだ。 東洋の香料、スペインのレース、珍しくエジプトの絨毯まで手に入った。
「ミリアムの喜ぶ顔が見たい」
まじめな働き者のシメオンが、唯一道楽にしているのは、一人娘を思い切り着飾らせることだった。
だんだん暗くなってきた。 いつまでもこうしているわけにはいかない。 やむを得ず、荷物の半分だけでも肩に担いで、くの字になって歩き出したとき、突然目の前に人が降ってきた。
風のせいではない。 盗賊の来襲だった。 熟れた実が落ちるように次々と、高い木から屈強な男たちが飛び降りてきて、見る間にシメオンは囲まれてしまった。
親玉らしい男が進み出て、腹の底から出る声で言った。
「持ち物すべて置いていけ。 命までは取らない」
「お願いです」
足は恐怖でふるえていたが、せめてレースだけは娘に持って帰りたかった。
「子供のものなんです。 この……この小さな包みだけでも」
「だめだ」
無情な声がさえぎった。
「この森を通る者はみな、通行税を俺たちに払うんだ」
親玉が手で合図すると、男たちはいっせいにシメオンに飛びかかり、荷物どころか服まではいでしまった。 シメオンはじたばたして泣き声をあげた。
「あんまりだ! これから冷えてくるというのに、この格好では凍え死んでしまう」
「それなら今死ね!」
無情な短剣が振り下ろされようとした。 シメオンは思わず眼をつぶった。
だが、冷たい刃は降りてこなかった。 代わりに足音が遠のいていったので、シメオンはぎゅっと閉じていた眼をおそるおそる開いてみた。
周囲を取り巻いていた盗賊たちは、ひとりもいなくなっていた。 その代わりに、粗末な黒服をまとった巡礼が立っている。 盗賊がシメオンから強奪した品々は、巡礼の足元に散らばっていた。
何が……何が起きたのだろう。 わけがわからず、ほとんど丸裸で放心しているシメオンに、巡礼は服を拾って渡してくれた。 はっと正気づき、急いで手を通しながら、シメオンはまた涙がにじむのを感じた。
「奇特なお方だ」
巡礼は無言で顔を振り向けた。 シメオンは服の汚れを払ったのち、男に最上級の礼をした。
「わたしたちヘブライの民に石を投げる者はあっても、親切にする者などほとんどおりません。 金貸しだと低く見下げているのです」
巡礼は初めて口を開いて、場違いなほど静かに答えた。
「神の前ではみな同じです」
「その神がそもそも違うのだから!」
シメオンは苦笑した。
巡礼はまだ気絶しているロバのところへ行き、拳を鋭く胸に入れた。 とたんにロバは激しく身震いし、目をあけた。 シメオンは歓喜した。
「生き返った!」
「さあ、早く行きましょう」
物に動じない巡礼にうながされて、シメオンはあわててロバの手綱を引きながら歩き出した。
アイルマーと同じ道筋にあるため、ふたりとも行き先はローダムだった。 その町外れに、シメオン・レヴィの家はあった。 ローダムに入る通り道なので、シメオンはどうしてもと言い張って巡礼を家に誘った。
「差し支えなかったらお泊りください。 肉はウサギぐらいしかありませんが、できるだけおもてなしします」
「納屋でけっこうです」
巡礼は低く言った。 シメオンは色をなした。
「とんでもない! 命の恩人にそんな!」
普通の家だった。 シメオンは実は金持ちだが、贅沢はしていない。 目立つようなことはしないのが、異国人としての知恵だった。
前庭に入ると、とたんに二階の窓から花のような声が降ってきた。
「お父様!」
帰りが遅いのをずっと心配していたらしい。 後に続く客に気付かず、ヴェールを額に上げたままで、少女が階段を軽々と駆け下り、一気に玄関から飛び出してきた。
「お帰りなさい!」
「ただいま」
シメオンは飛びつく娘をしばし抱きしめていたが、やがて客人を思い出して急いで娘にヴェールをかけてやった。
「ミリアム、実はお客さんを連れてきてね」
淡い黄色のヴェールの陰から利発そうな眼をくりくりと輝かせて、ミリアムは巡礼に挨拶した。
「ようこそ」
巡礼は無言で頭を下げた。 少し下を向いているのでますます頭巾が顔にかかり、まったくといっていいほど目鼻立ちが見えない。 それでもミリアムは不審がるそぶりは見せず、巡礼にほほえみかけた。
「冷えてきました。 さあ、中へどうぞ!」
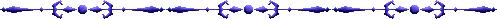
 |
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
